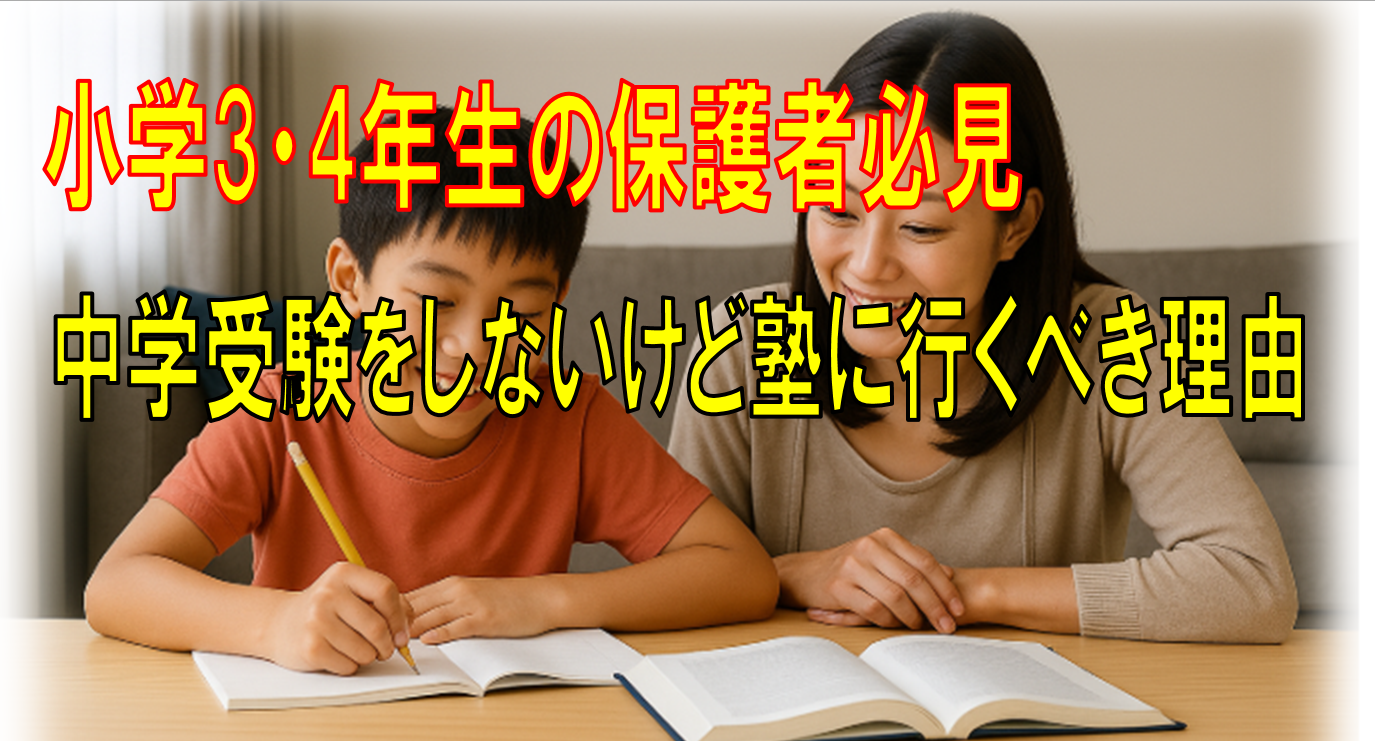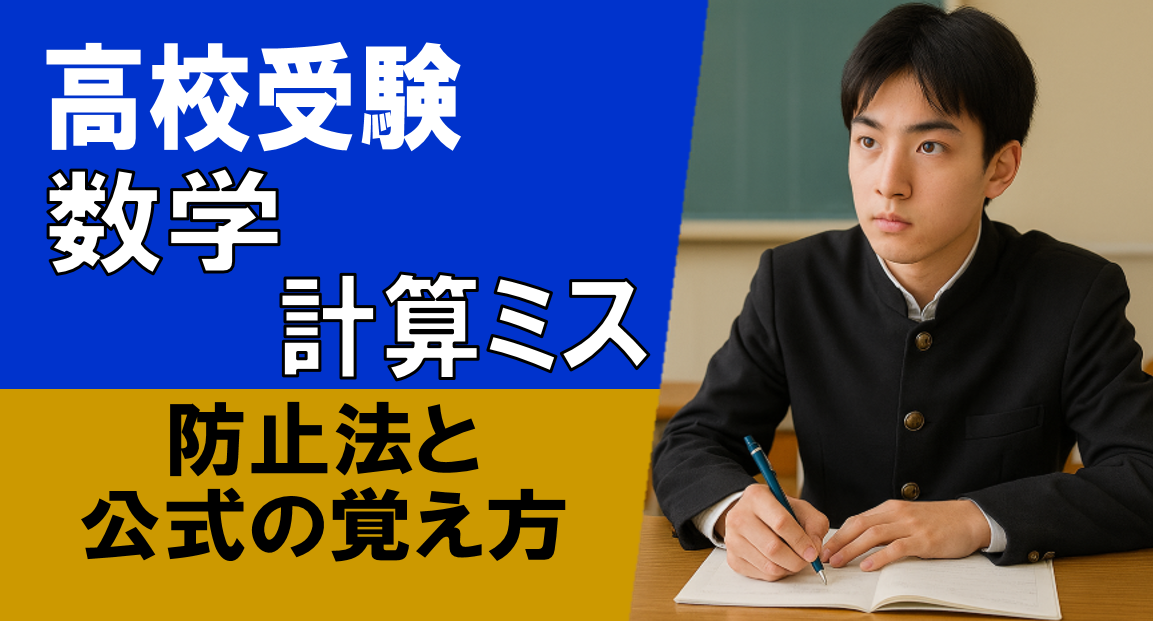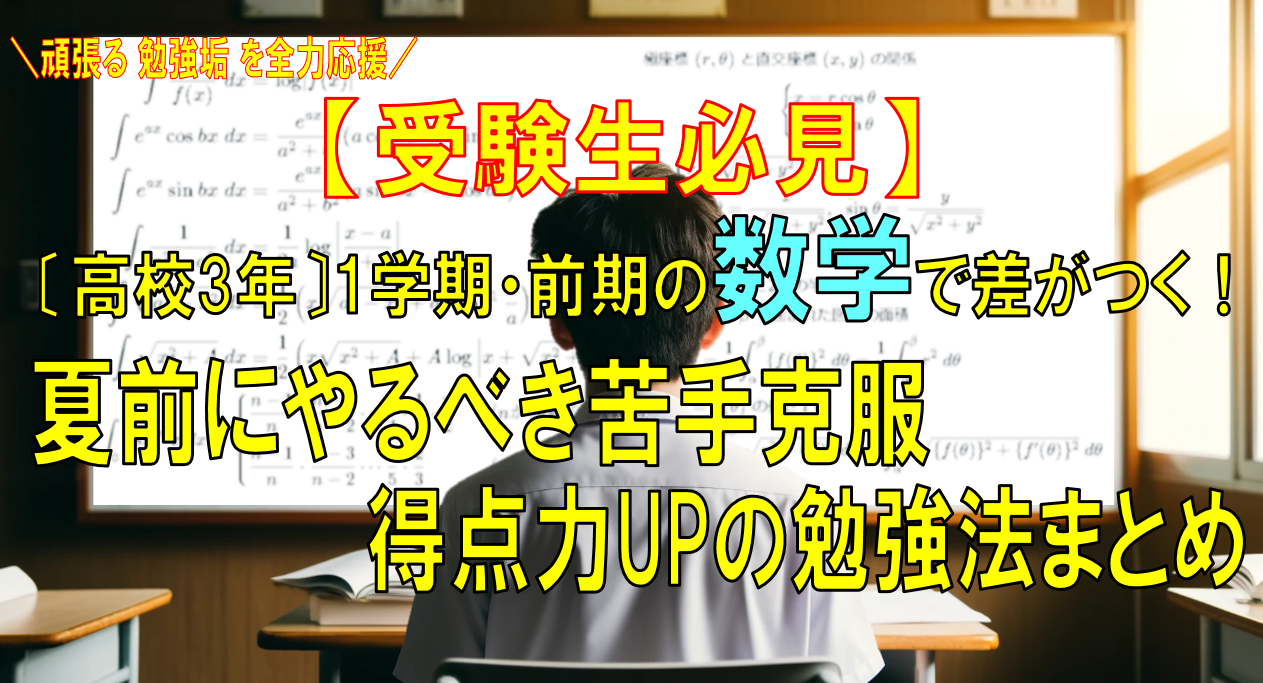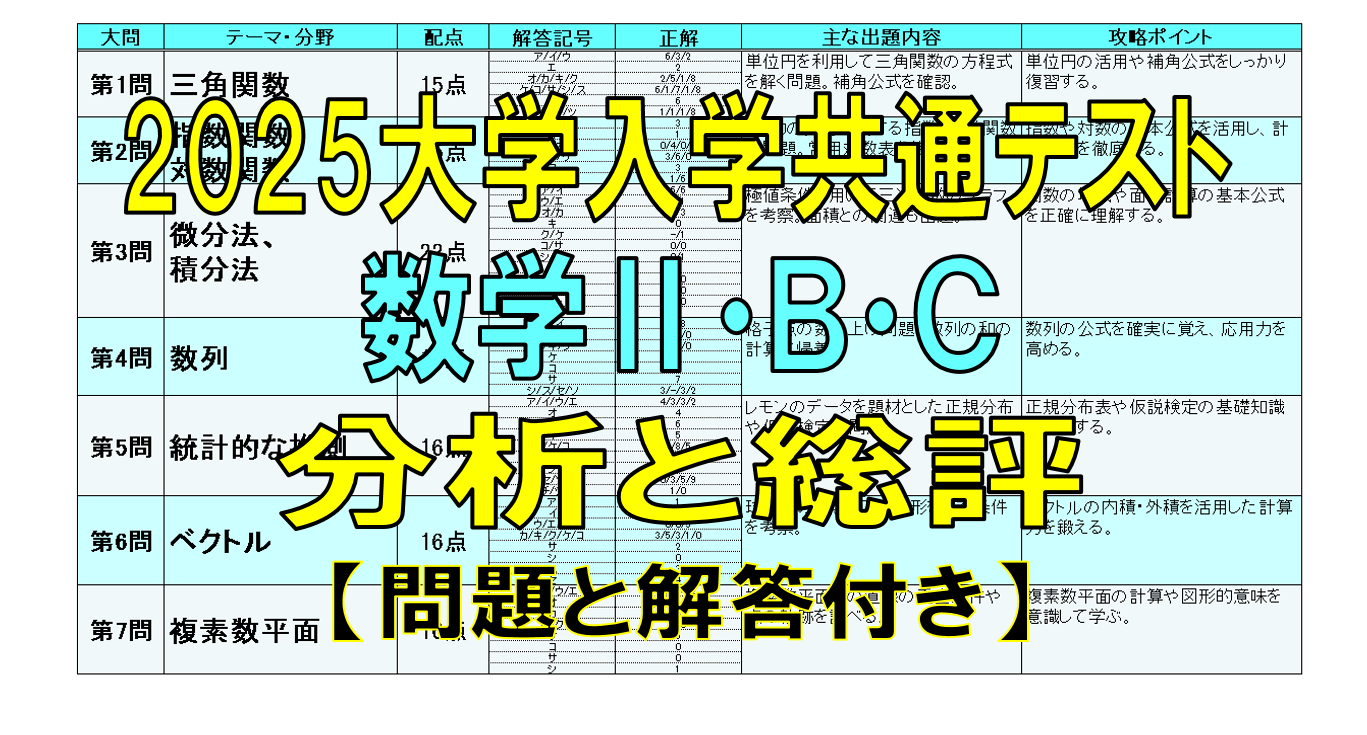①集団授業形式
②個別指導形式
③自学型形式
④映像授業形式
⑤オンライン形式
⑥集団授業と個別指導をミックス
⑦映像授業視聴⇒個別指導
があります。
それではこの①~⑦を具体的に解説します。
①集団授業形式
集団授業形式をさらに3つに分類できる。
人数定義はありませんが、私は次の3つに分類している。
【1】3名~6名の少人数制授業
【2】7名~20名の集団授業
【3】21名以上の大集団授業
ではこの3つをさらに詳しく解説します。
解説
【1】3名~6名の 少人数制授業
メリット
・個々の学力に合わせたクラス設定
・同じ中学校を1クラスにして○○中の定期テスト対策などが可能
・偏差値別に○○学校受験対策などが可能
・細部の理解度まで講師が都度、把握することが可能
デメリットや要注意事項
・少人数制と謳いながら、1クラス10名以上生徒がいるケースは要注意
・生徒が集まらない塾がこのフレーズを使って、良く見せる傾向がある。
生徒が集まる塾では、規定人数に達したら募集を打止めにするか、
規定人数を超えたらクラス数を増やしている。
従って、定員設定が曖昧かつ、1クラス設定で長期間、少人数制を謳っている塾は要注意。

解説
【2】7名~20名の集団授業
メリット
※授業力の高い講師が担当になれば、以下の期待ができる。
・競争原理を使って、背伸びをしっかりとさせる。
・全体の中での自分の立ち位置を把握できる。
・人生論、説得を聞きモチベーションが上がる。
・発問が多く、集団の中にいることを感じさせない。
・スピード感があり、遊べない。
・常に緊張感がある。
・宿題や小テストの状況を公開し手抜きができない。
・ライバルの存在で自分への負荷を上げることができる。
※上記が性格と合えば、相当なレベルアップが期待できます。
デメリット
・授業力の低い講師が担当になると上記の期待ができない。
・塾によっては、新人講師やアルバイト講師が担当になる可能性もあるので確認を。

解説
【3】21名以上の大集団授業
ベテラン講師、授業力の高い人気講師が担当することが多い。
講義型の授業になる。
★ポイント★管理がゆるい中でも講師の言う通りの事を実践出来る事が重要。
自己をコントロールして、自分に厳しくできる事が重要。
メリット
・講師からの貴重な人生論、説得はしっかりと練ってられており良い影響を受ける。
・ある程度優秀であれば、その中でトップを目指すというモチベーションになれる。
・授業料が比較的安価になるので、多くの科目や単元の講義が受けやすい。
デメリット
・講師の話術でレベルアップしている錯覚に陥りやすい。
・多くは座席は自由で緊張感がない。
・生徒管理や宿題管理はほぼ不可能。
・発問→指名→返答の方式はほぼ不可能。
・集団に紛れて緊張感が低下する者は不適。

②個別指導形式
講師の多くは学生アルバイト。
生徒保護者もそれは前提として把握している状態がスタンダード。
新人講師も多い。ベテラン講師も混在する。
※担当講師の力量により、効果にかなり差がでるのでしっかりと担当を確認したい。
社員スタッフは1校舎に1名か2名。
塾長1名の教室は塾長はほぼ授業はしない。授業をすると運営が回らなくなる。
しかし、講師不足などで授業に入ることもある。これが頻繁に起こる教室は危険。
塾長以外の社員スタッフがいる教室は、
かなり生徒を集めている塾か、新人社員の育成であるケースが多い。
個別指導でもさらに3つに分類できる。
人数定義はありませんが、
【1】1対1(講師1:生徒1)
【2】1対2(講師1:生徒2)
【3】1対4(講師1:生徒4)
と3つに分類。以下に詳しく解説します。
解説
【1】1対1(講師1:生徒1)
メリット
・付き切りで見てもらう事ができる。
・個々の間違えの特徴をしっかりと把握してもらえ、その対策を受けられる。
・難関校特化型、基礎確認や学力不振、特殊な事情の場合にもこの指導が適切。
デメリット
・生徒によっては、講師に常に見られている感覚に耐えられなく敬遠される。
※講師側もその配慮で演習問題の準備をするケースもある。
・慣れあいの仲になりやすい。(講師にもよる)
・授業料は当然高い。

解説
【2】1対2(講師1:生徒2)
個別指導でのスタンダードの形式。
同じ学年、学力レベル、友人同士をペアにして授業をすることが多い。
講師側としては、1度で2名を同時に指導できるから授業がしやすい。
学年の違い、学力レベルの違いがある生徒がペアになる場合は、他方が演習中に他方を解説する。
メリット
・友人同士での受講希望による安心感。競争意識の向上。
・逆に友人同士をペアにしないでほしいという保護者様からの要望もあり。
デメリット
・友人とのペアで、講師と慣れあいの仲になり集中力が欠ける。(講師にもよる)
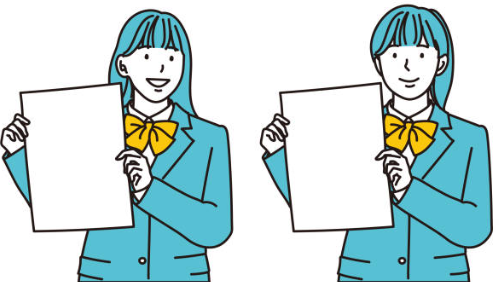
解説
【3】1対4(講師1:生徒4)
相当力のある講師でないと難しい。
アルバイト講師が圧倒的に多い個別指導型では、
1対4の場合、生徒管理が行き届かず、
お喋り中心となってしまったり、
生徒側に主導権を奪われるケースも多い。
また4名それぞれが、学年が違ったり、科目が違ったりすると、
管理が相当キツくなり、放置される時間が多くなる。
授業料は抑えられるが、お勧めしない。
メリット
・安価であること
デメリット
・同じ学年、学力レベルが同じ4名が揃えば、
講師側としては都合がいいが、なかなかそうならない。
・3名が友人同士で、1名が学年も違う状態になると、
その1名の生徒はやりづらい気持ちになる。
※そこまで配慮できる講師であれば良いが。

③自立型形式
1対多(講師1:生徒多)
解説
以下の生徒であれば、効果的です。
・与えられた課題を集中して黙々と取り組める
・多少の疑問点は自ら調べる力がある
・きちんと質問できる
メリット
・時間や曜日の細かい指定がない塾が多い。
・曜日指定があっても時間は自由度が高い。
・部活動や習い事の併用はしやすい。
デメリット
多数の生徒がそれぞれの課題をこなすので、
講師1名(数名)が、1人の生徒をじっくりと見てあげえることは厳しい。
その為、課題を黙々とこなし、
疑問点が生じた場合は自ら調べる力が必要となる。(実際これができる生徒は伸びます。)
もちろん質問をどんどん積極的にすることもできますが、
定期テスト前は、多くの生徒が質問を抱えているので、
講師は引っぱりだこになる。
その中で、質問できる生徒と質問できない生徒がいる。
※講師側は質問できない生徒にしっかりと声がけをするなどの配慮をしている。

④映像授業形式
過去の映像配信は、塾に行ってビデオやDVD、専用端末からの視聴であった。
この頃まではカリスマ講師の映像授業も流行であった。
2012年〜2014年頃から、スマホや4Gの影響で、
映像配信化が進み授業映像をどこでもダウンロードして
視聴出来る時代となった。
プロ講師でなくてもYou Tubeで授業をアップする人も増えた。
メリット
・どこでも、いつでも視聴できる
・何度も視聴できる
・再生速度を変えられる
・必要な部分だけを視聴できる
・安価・通塾しなくていい(送迎しなくていい)
・生徒同士の人間関係を気にしなくていい
デメリット
※ほど良い緊張感がないので強い覚悟が必要です。
・楽過ぎるので、だらける
・他人と比較できない
・ライバルがいない
・ネット環境

⑤オンライン授業形式
2019年までは、今後拡大傾向にある可能性は
多くの塾関係者は思ってはいたが、
やはり生の授業が大切だという考えの講師も強く
オンライン反対派も多かった。
しかし、2020年初頭のコロナをきっかけに
爆発的にオンライン授業の需要が高まり、
オンラインに後ろ向きであった塾も
こぞってオンライン授業を開始をした。
ここで、勝ち残った塾と経営難となる塾に大きく別れた。
勝ち残った塾の特徴は、コロナ禍前から映像授業をしていた。
そうです。このオンライン授業においては、
オンライン授業+映像授業ができる塾は勝ち残る状態になった。
メリット
・通塾しなくていい(送迎しなくていい)
・全国どこにいても一流の授業が受けられる
・保護者の目の届く範囲で受講できる
・保護者の不在時であっても受講できる
・生徒同士の人間関係を気にしなくていい
・時間の融通が利く
デメリット
・ネット環境対応
・家のどこでやるか
・集団の場合、①集団授業形式と同じ

⑥集団授業と個別指導をミックス
上記の集団授業と個別指導の特性を両方を兼ね備える。
塾によって選択の幅があり、
【1】セット受講が基本の塾
【2】集団授業メインで個別指導をオプション塾
【3】個別指導メインで集団授業をオプション塾
という形に3つに分類できる。以下にその3つを解説します。
解説
【1】セット受講が基本の塾
小規模経営塾に多い。
少人数の集団授業の後に、
個別指導1対1(講師1:生徒1)で
・苦手克服のとして個別指導でしっかりとフォロー
・より応用や発展まで手を伸ばし高度な内容
上記のどちらかに該当する場合は、
細部にわたっての面倒見の観点から、個人的にはオススメできると思っています。
解説
【2】集団授業メインで個別指導をオプション塾
集団授業と個別指導の両方を事業としている大手塾に多い。
集団授業をメインとして、科目で選択して個別指導を追加受講するイメージになる。
個別指導を担当している講師が、
集団授業の細かい内容までしっかりと把握しているのかは、
確認すべきポイントとなる。
個別指導の講師の力量によって大きく効果が変わる。
メリット
ここで良い講師が担当となれば、【1】と同様に細部までの面倒見が期待できる。
デメリット
ここで注意すべき点として、
大手塾の場合、集団授業の講師と個別指導の講師が違うことはよくあるが、
両者の連携がきちんと取れていないとムダな個別指導を受ける事になる。
(集団授業は力のある講師が担当して、
個別指導を新人アルバイト講師が担当するというのはよくある。)
解説
【3】個別指導メインで集団授業をオプション塾
通常は個別指導であるが、
・理社
・季節講習などの特別講座
・定期テスト対策
を集団授業で実施する形態となる。
メリット
全ての講義を個別指導で受講するのは、『時間的』にも『費用的』にもキツイが、
メインとなる英数国の個別指導として、
それに加えて上記を集団授業として受講できるので負担が軽減される。
(塾側としても、講師不足解消や短期間開催ができる。)
デメリット
逆にこれらも全て個別指導を希望することができない可能性がある。
⑦映像授業視聴⇒個別指導
映像授業を視聴後に、その授業内容を個別指導でフォローとして補習。
もしくは演習や発展内容へ広げる。
個別指導塾に、この形式を取り入れた塾が多い。
メリット
この形式を導入することで、簡単な導入授業を省くことごでき、
生徒にとっても講師にとっても効率良い。
その為、採用している塾も増えている。
※反転授業ともいう
【番外】反転授業の意味
従来の「授業」と「(復習の)宿題」の役割を逆にした授業形態で、
生徒は新たな学習内容を、動画授業を予習として視聴し、
教室では導入は行わず、従来より長く演習時間を確保したり、
(クラスによって)応用問題まで拡張することができる形態の授業。