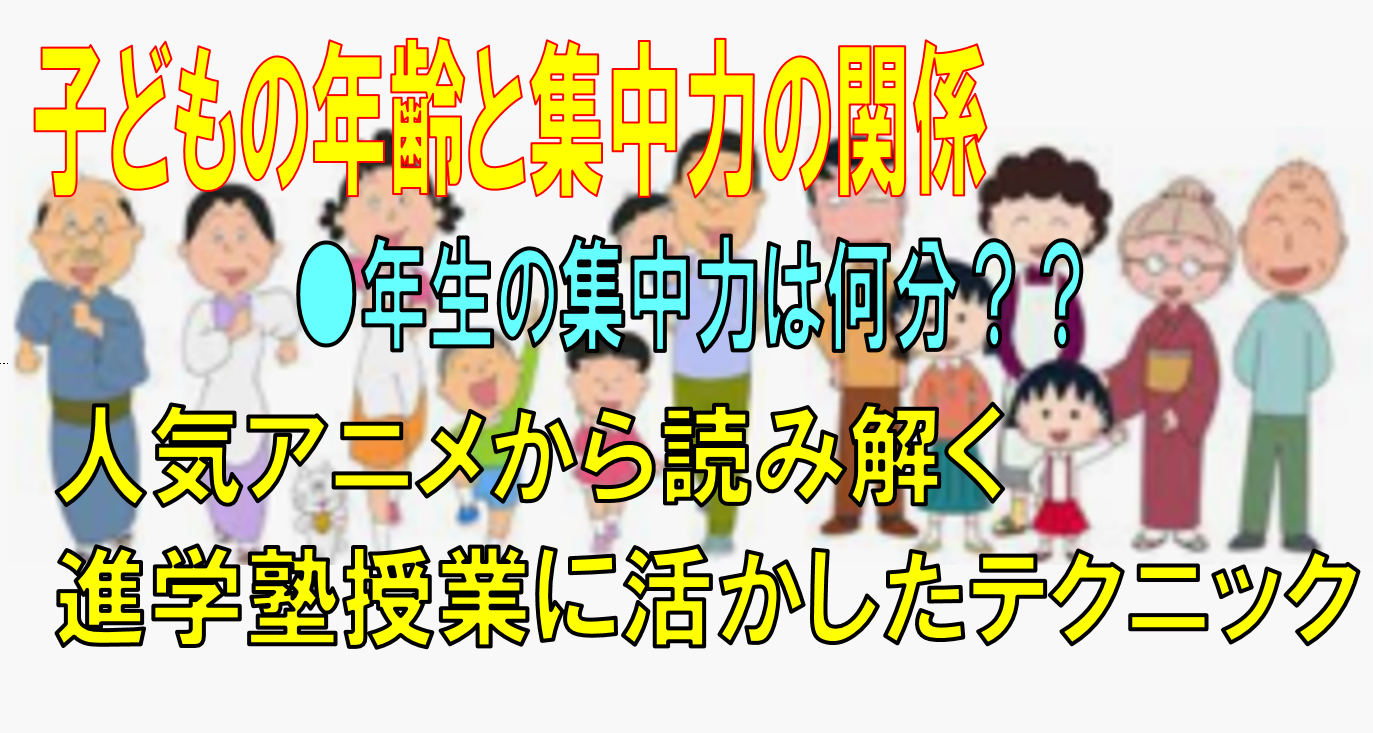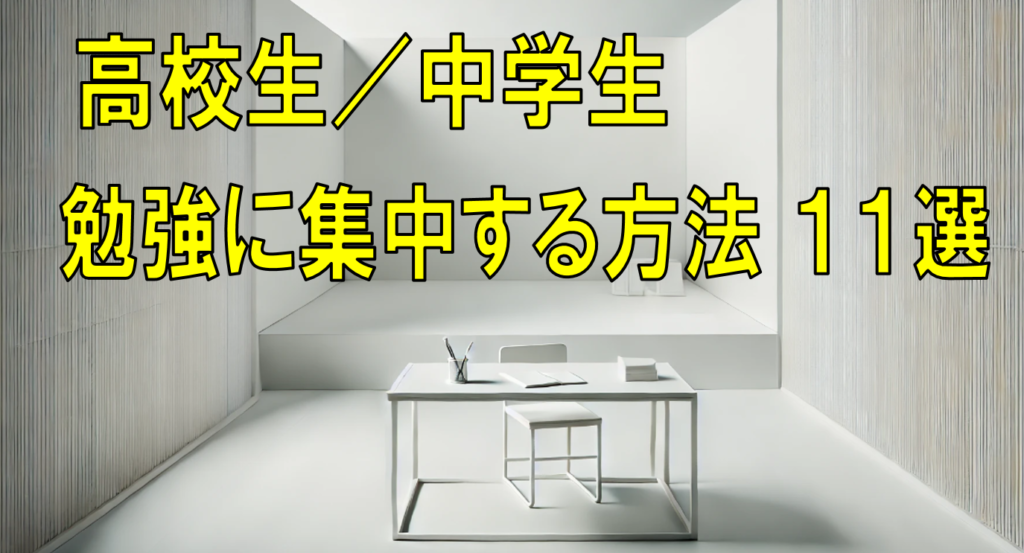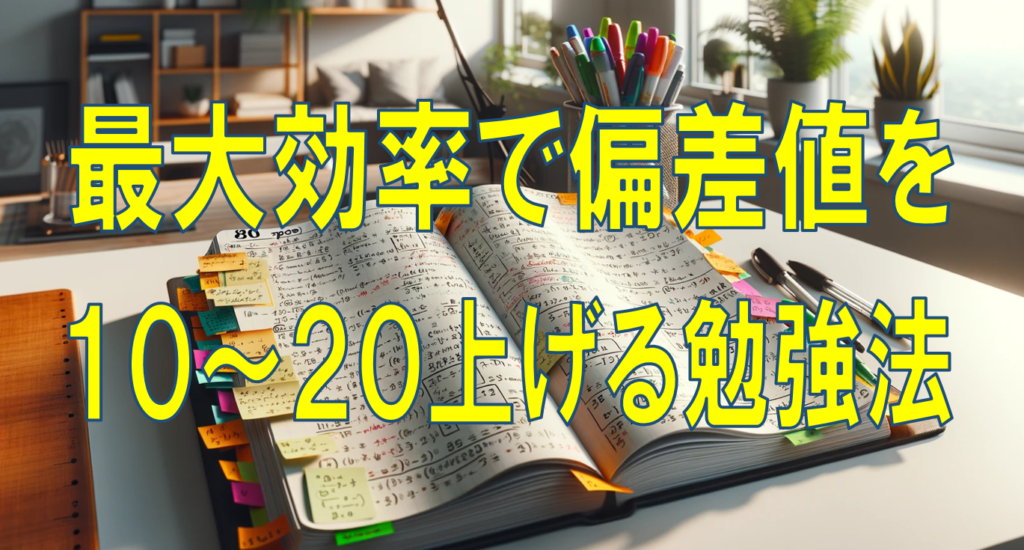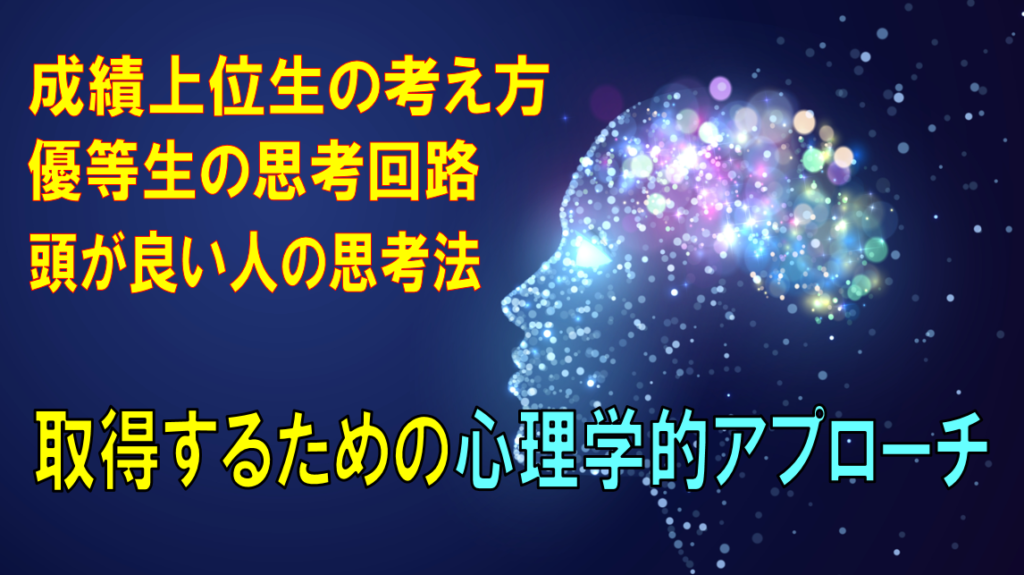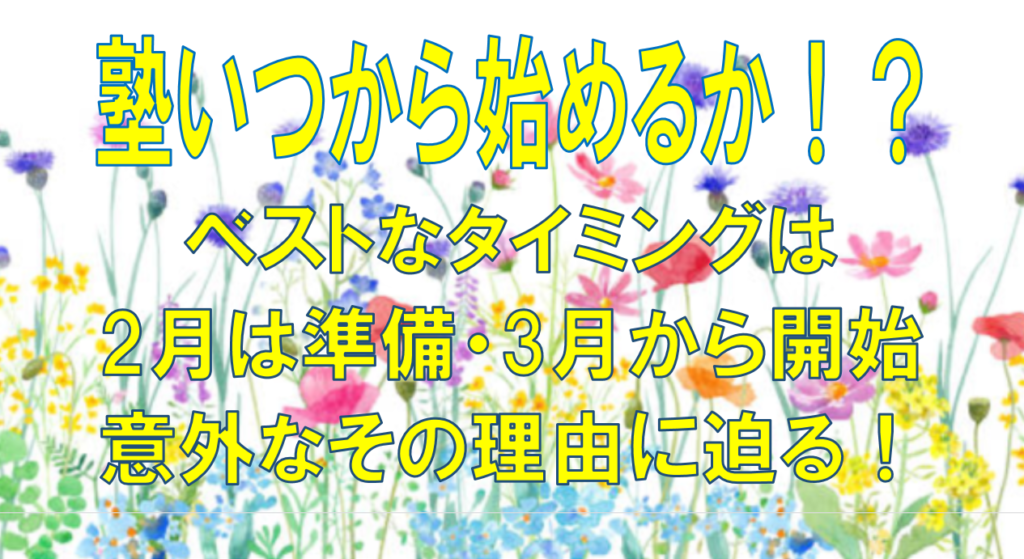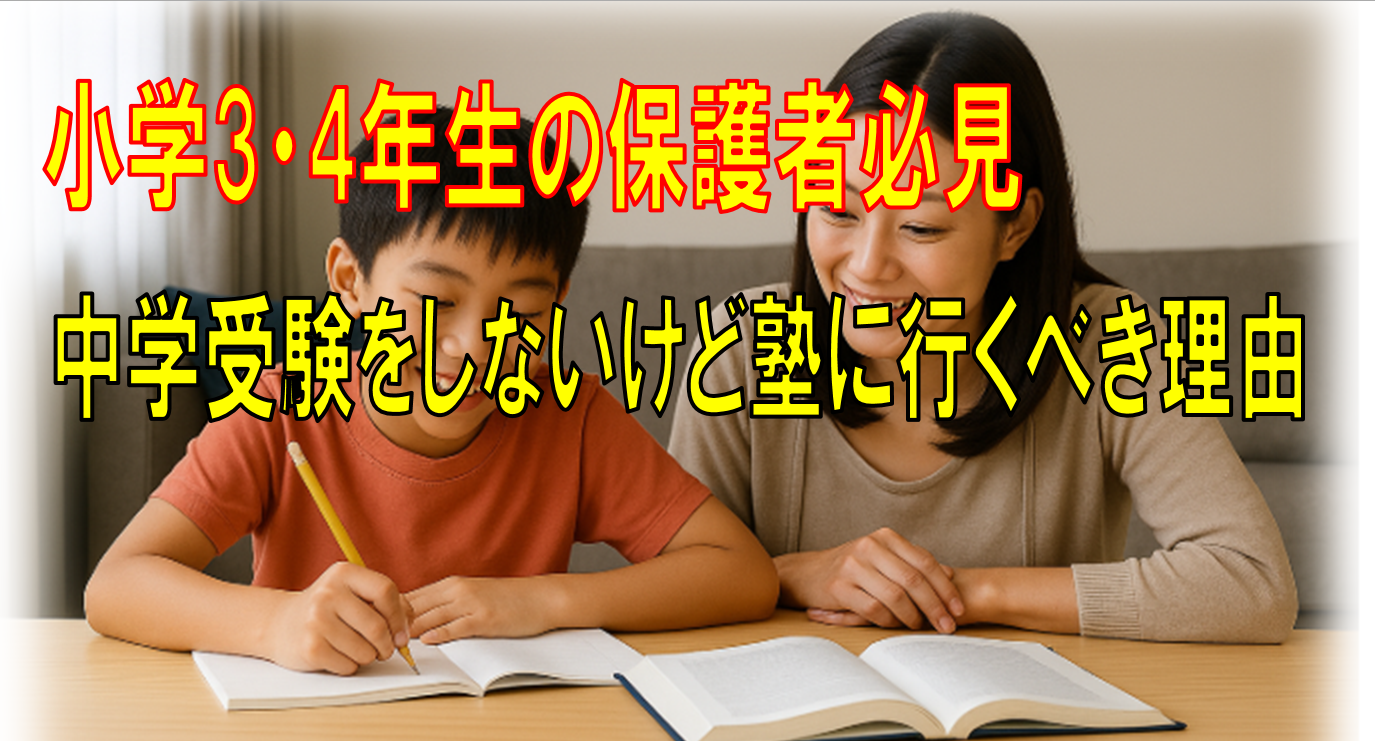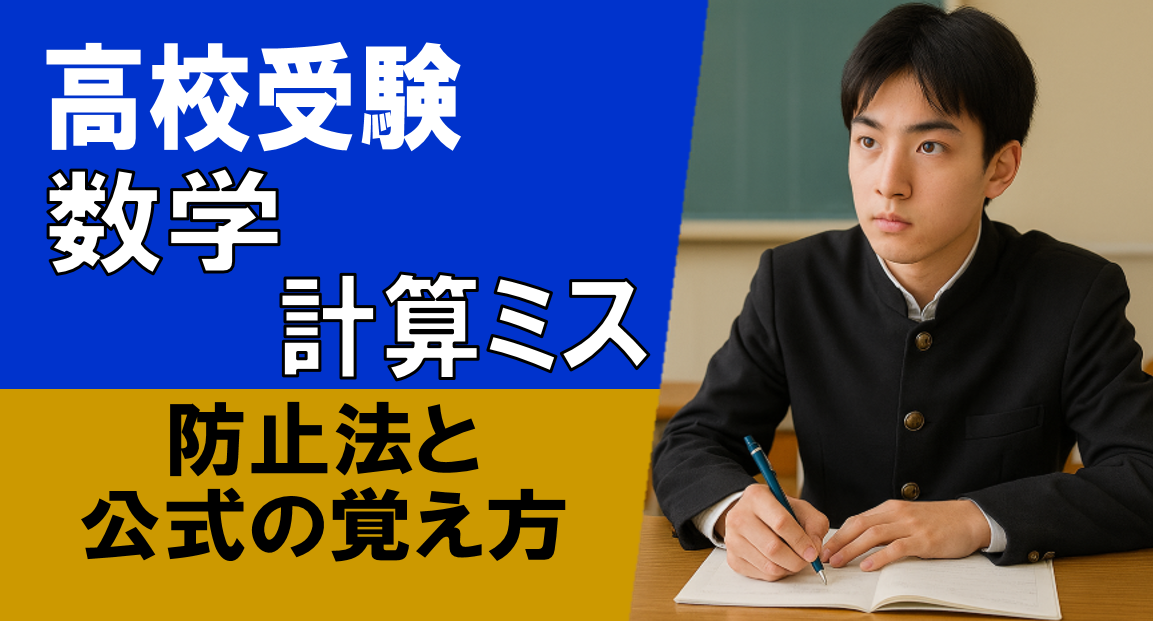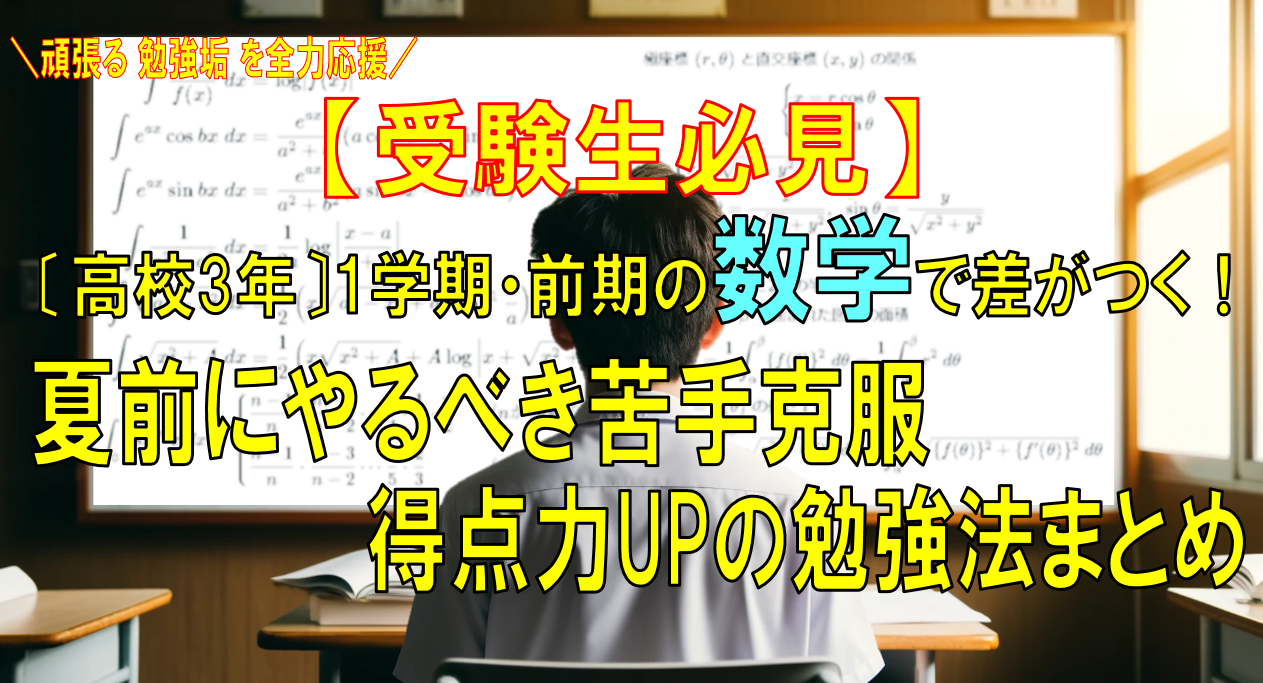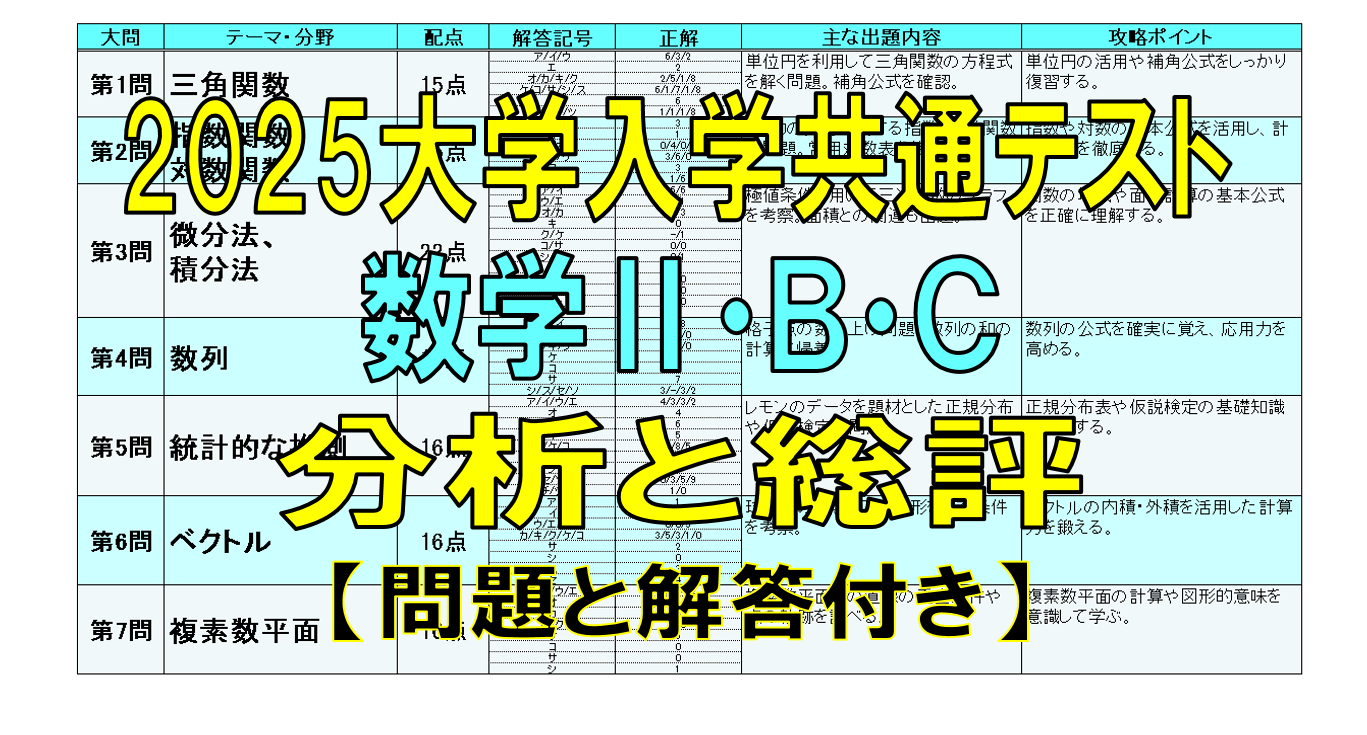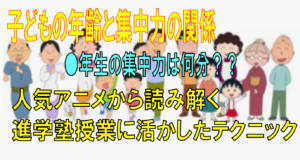1. 子どもの集中力は年齢に依存する
子どもたちの集中力は年齢に大きく依存します。具体的には、
- 未就学児から小学校低学年の子どもは「年齢プラス1分」程度の集中力しか持続できません。
- 小学校高学年でも、特別な学習習慣が無い場合は、通常では集中できる時間は約15分程度です。
このことからも、子どもに長時間の集中を期待するのは無理があります。そのため、学習の内容やタスクは5分から10分程度で完了できる小さな単位に分けて取り組むことがポイントです。これにより、集中力の途切れを防ぎ、達成感を得やすくなります。
2. テレビ番組から学ぶ時間配分のコツ
私たちが日常的に目にするテレビ番組は、集中力を保つために巧妙に設計されています。多くの番組は15分おきにCMが入る構成です。

例えば、
子どもたちに人気の「ちびまる子ちゃん」では、1話が12分、2分のCMを2回挟むことで、集中力が持続するよう設計されています。
また「サザエさん」も同様に、1話が7分、CMが2分で、合計30分にまとめられています。
学習も同様に、集中力が切れる前に一度区切りをつけ、次のタスクに取り組むことで効果を高められます。
3. 効果的な授業構成:学年とクラスに合わせたカスタマイズ
私の長年にわたる塾講師としての経験から、子どもたちが集中できる時間を考慮して授業を組み立てることが、学習成果を最大化する秘訣です。各学年やクラスの特性を考慮し、適切なタイミングで休憩を挟んだり、時には雑談を交えたりして生徒の集中を維持します。これには、単なる授業以上の「サービス精神」が必要です。生徒一人ひとりのやる気を引き出すためには、授業の進め方に工夫が求められます。
4. 効果的な授業の5つのステップ
私が考える理想的な授業構成は、以下の5つのステップで成り立っています。
- 冒頭モチベーション形成:授業の初めに、生徒のやる気を引き出すための導入を行います。前回の授業内容の確認や、授業の目的を明確に伝えることで、今日の学びに対する興味を高めます。
- 確認テストと宿題確認:前回の宿題や学習内容を確認し、テストを通じて理解度をチェックします。これにより、生徒自身が自分の成長を実感できるようにします。
- 導入と展開:新しい学びに入る前に、ウォーミングアップとして生徒の身近な話題を取り入れ、授業内容に関連づけます。これにより、授業への興味と関心を引き出します。
- 演習と解説の繰り返し:授業中に発問や指名を行い、理解度を確認しながら進めます。適切なタイミングで区切りを入れ、演習を通じて学びを定着させます。
- まとめと振り返り:最後に授業の内容を振り返り、重要事項を再確認します。次回の授業への準備として宿題の内容や予告を行い、生徒が学びを継続できるように導きます。
5. 子どもの自己肯定感を高める教育心理学的アプローチ
授業の進行中に、発問や演習を繰り返すことで生徒が「できた」「わかった」という達成感を味わえるように工夫しています。教育心理学では、この達成感が自己肯定感を高め、学習意欲を持続させる重要な要素とされています。自己効力感が高まると、生徒はさらにチャレンジ精神を持ち、難しい問題にも積極的に取り組むようになります。これが継続的な成績向上につながるのです。
6. 適切な演習時間の設定とその効果
演習時間の設定も重要です。短時間で瞬時に答えられるような問題は、生徒に成功体験を提供します。一方、長めの演習時間では、論理的に考えさせる問題を出すことで、思考力を鍛え、より深い学びを促します。このように、子どもの集中力と考える力をバランスよく引き出すためには、授業の時間配分を工夫する必要があります。
7. 終わりに:プロの塾講師に求められるサービス精神
最後に、私たちプロの塾講師は、単に知識を教えるだけでなく、子どもたちの成長を支える存在でなければなりません。授業の中で集中力を引き出し、達成感を味わわせ、自己肯定感を高めるためのサービス精神を持ち続けることが、長期的な成功につながるのです。私自身も長年間の塾講師経験を通じて、この大切な役割を常に意識してきました。これからも、子どもたち一人ひとりの個性や状況に寄り添い、最適な授業を提供していきたいと思います。