本業は塾講師なので、その経験を生かし、私自身の小学1の息子の勉強もサポートしながら、日々悩みながらも取り組んでいることがあります。息子はマイクラとマリオに夢中で、ゲームの虜になってしまうことがしばしば。。。
そんな毎日ですが、上手に勉強の時間と、ゲームの時間のバランスを取りながら取り組んでいます。
小学1年生のお子さんの算数と国語の勉強がうまくいかなくて悩んでいるママパパ必見!
有効な勉強法と宿題の対策をお伝えします。
小学1年生の算数の勉強方法
1学期のうちは相当スローペースです。幼稚園生でもできるレベルの絵を見て、数えて書くことの繰り返しなので、優しすぎて少々不安になってしまうこともあるかもしれません。ところが、夏休み前後からどんどん進んでいきますので、しっかりとこれから先がどのような流れになっていくのかを把握しておくことが大切です。
親と一緒に勉強を楽しくやり、習慣が身につくようにしていきましょう。
また、日常の中で算数の応用例を見つけることで、楽しく学ぶことができます。買い物でのお金の計算や料理の分量計算など、身近な場面で算数を活用しましょう。
1. 1学期はワクワク感を育てる
とにかくワクワクしながら、好奇心を持ってもらい、楽しくお勉強をすることが大切です。
そして小学1年生は基礎の基礎が大切です。足し算や引き算の基本を身につけるために、1学期のうちは、数字だけでなく「絵」や「具体的な事例」を結びつけて問題を一緒にやってあげることで楽しさやワクワク感を育てて、勉強は楽しい事であると認識してもらうようにします。
「算数=嫌なも」のとならないように導く重要な期間です。決して怒ったりせず、気持ちが乗らないときは大目に見るという気持ちも大切です。
2. 2学期(夏休みから)は徐々に問題量を増やす
1桁の足し算、1桁の引き算を指を使わずに瞬間的に答えることができるようにしてあげましょう。
初めは算数セットに入っている単語帳を使って「親がめくる」→「子供が答える」
これを毎日の日課にして繰り返します。
最初は大変ですが、「いいね!」「早い!」「すごい!」などの前向きな言葉をどんどん言ってあげるようにします。するとスピードがどんどん上がってくるので、タイマーを使って「●月●日:〇分〇〇秒」を毎日記録するようにしてあげます。
記録として見える化をしてあげることで、より子供のモチベーションアップにつながります。徐々にスピードが上がってきて、ある程度になると「昨日より遅かった!」とかで悔しがったり、時には泣いてしまったりしますが、その悔しがることも思いっきり褒めてあげるようにしましょう!
1桁の足し算、1桁の引き算がある程度のスピードでできるようになったら、2桁と1桁の足し算、引き算にもチャレンジさせるようにします。
また、「単語帳で口で答える」から「鉛筆で答えを書く」へのレベルアップもさせるようにします。
13+6や16-9などの問題を素早く丁寧に解けるようにするために、問題集やプリントを使って繰り返し解くことがあたり前の状態にしてあげましょう。
3. 3学期(冬休みから)は問題集やプリントを使って繰り返し
大きい数として「100までの計算」ができるようにします。70+20などの問題になります。一の位は0で十の位どうしを計算することを身に着けます。
また、ここまでの計算が今後の算数(計算)の基礎となるので、同じ問題集でも構いませんので再購入して、何度も繰り返して演習量を増やしてください。やればやるほど、どんどん早くなっていきます。問題を見た瞬間答えの数字が浮かぶようになったら、今後算数が大好きになることでしょう。
以下、オススメの問題集です。
| たしざんおけいこ 2集 (幼児ドリル かず・けいさんシリーズ) [ くもん出版編集部 ] 価格:726円(税込、送料無料) (2023/12/5時点) 楽天で購入 |
小学1年生の国語の勉強方法
ひらがな、カタカナ、漢字(小1は80文字)の書き順、とめ・はね・はらい、バランスの基礎となるのが小学1年です。
また文章を読んで、問題に答える文章読解の問題も小学1年からあります。教科書の文章の問題に加えて、初見の文章読解の問題も小学1年からあります。初見の文章読解の問題をどの時期に取り入れるのかは学校の先生の裁量に任させています。
自分の息子のクラスは、初見の文章読解の問題は3学期にやるそうですが、その他のクラスは2学期にやって、壊滅状態だったそうです。。。担任の先生によってバラバラです。
1.音読は親がしっかりとその重要性を理解して、一緒にやることが大切
小学1年生のお子さんが成長する中で、音読は非常に重要です。
まず正しい姿勢を意識します。文字を追い、間延びせずに語尾を言い切り、言葉に音を付けながら読むことで、言葉の理解力や語彙力が向上します。これは将来の読解力や文章理解力を築く上での基盤となります。また、正しい発音やリズムを学ぶことで、豊かな言語表現力が養われます。
短い文章から始めて段々と難易度を上げることで、お子さんの集中力も向上します。音読は学習における興味を育み、学校生活全般においてプラスとなり、他の教科にも良い影響を与えます。
また親子のコミュニケーションを深める良い機会でもあります。日常に取り入れて、お子さんの学びのサポートを一緒に楽しんでください。
2. 文章の書き方や読み方のコツ(句読点、改行)
国語の基本となる文法ルールや表現方法を学ぶことは、文章を正確に、また読みやすくするために欠かせません。具体的には、文の終わりを示す句読点(。)や、文の区切りを意味する読点(、)の正しい使い方を理解することが重要です。句読点を適切に使用することで、文章はよりクリアで理解しやすいものになります。また、段落の切り替え(改行)にも注意を払いましょう。新しい話題に移る際に段落を変えることで、文章の構造が明確になり、読み手にとって追いやすくなります。これらの基本的な要素を学ぶことで、こどもは国語の力をしっかりと育てることができるでしょう。
3. 語彙力を伸ばすための保護者の活動
日常生活の中での会話は、新しい言葉に触れる絶好の機会です。普段の会話で意識して、少し難しい言葉や新しい表現を取り入れてみましょう。また、読書は語彙力を高めるのに非常に有効です。特に、子供向けの物語や図鑑を読むことで、楽しみながら様々な新しい単語に触れることができます。さらに、低学年向けの辞書や図鑑を使って意味を調べる習慣を身につけることも、語彙力の向上に役立ちます。また、単語カードを作成したり、クイズ形式のゲームを家族で楽しむことも、学習をより効果的で楽しいものにする方法です。これらの活動を通じて、こどもの言葉の理解を深め、コミュニケーション能力を豊かに育てていきましょう。
小学1年生の宿題の取り組み方3選
小学校に入学すると、こどもは初めて宿題という自己責任としての課題が誕生します。宿題に取り組む習慣を身につけさせるための3つの効果的な方法をご紹介します。
1.定期的な学習スケジュールの確立
宿題に取り組むための最初のステップは、一日のうち決まった時間を学習時間として設定することです。例えば、毎日夕食後の30分間を宿題の時間にするなど、ルーティンを作ることが大切です。規則正しいスケジュールは、こどもが宿題に取り組む習慣を身につけるのに役立ちます。
2.学習環境の整備
集中して宿題に取り組むためには、適切な学習環境を整えることが重要です。静かで明るい場所を選び、必要な学習道具(鉛筆、消しゴム、定規など)がすぐ手に取れるようにしておきましょう。また、デジタルデバイスの使用を限定し、学習に集中できる環境を作ることも大切です。
3.親子でのコミュニケーション
宿題を通じて、こどもとのコミュニケーションを深めましょう。宿題に取り組む前に、何をするかを話し合い、理解を確認します。また、完了後には成果を一緒に確認し、励ましや適切なフィードバックを与えることが大切です。このプロセスは、こどもの自信を育て、学習へのモチベーションを高めることに繋がります。
宿題はこどもの学習習慣を築く上で重要な役割を果たします。定期的なスケジュール、適切な学習環境、そして親子間のコミュニケーションを通じて、小学1年生のこどもが宿題に対する良い習慣を身につけられるようサポートしましょう。このような取り組みは、こどもの学習意欲を高め、今後の学校生活においても大きな力となるでしょう。

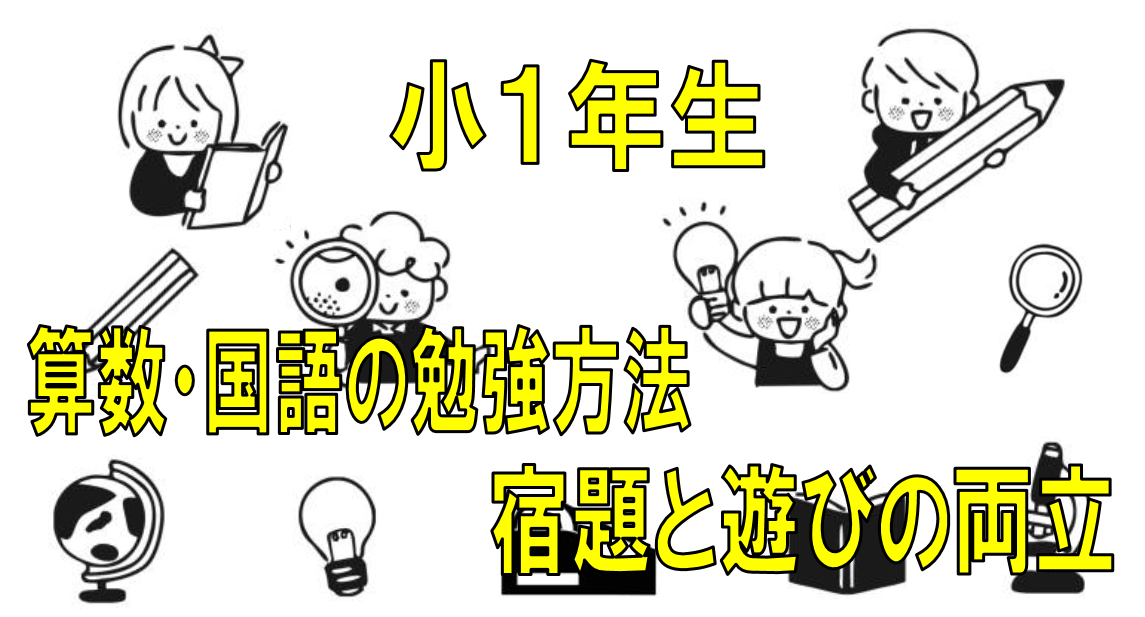
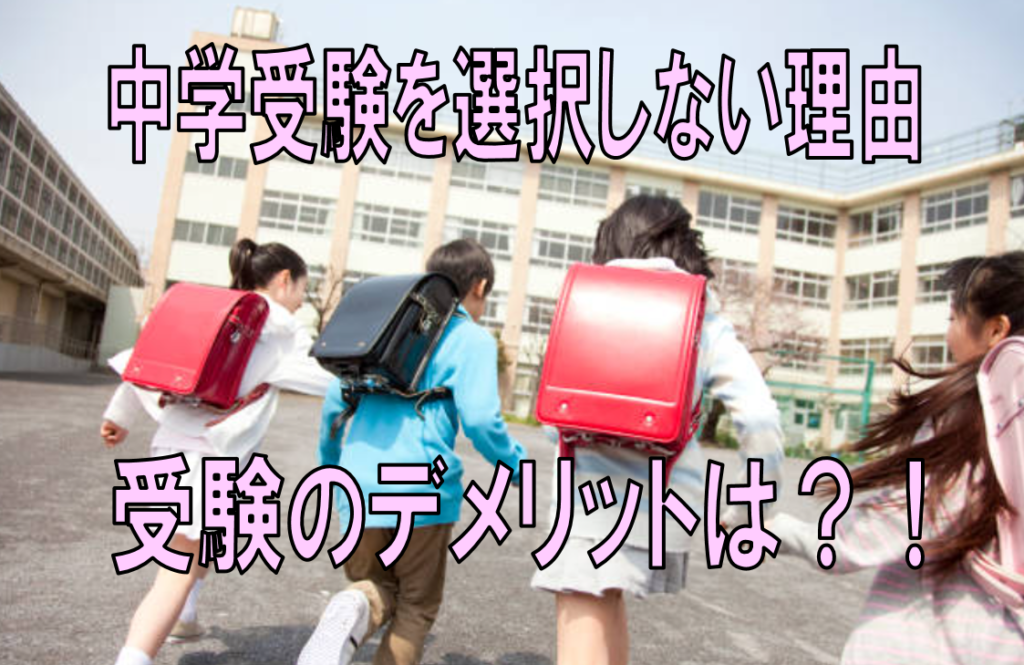
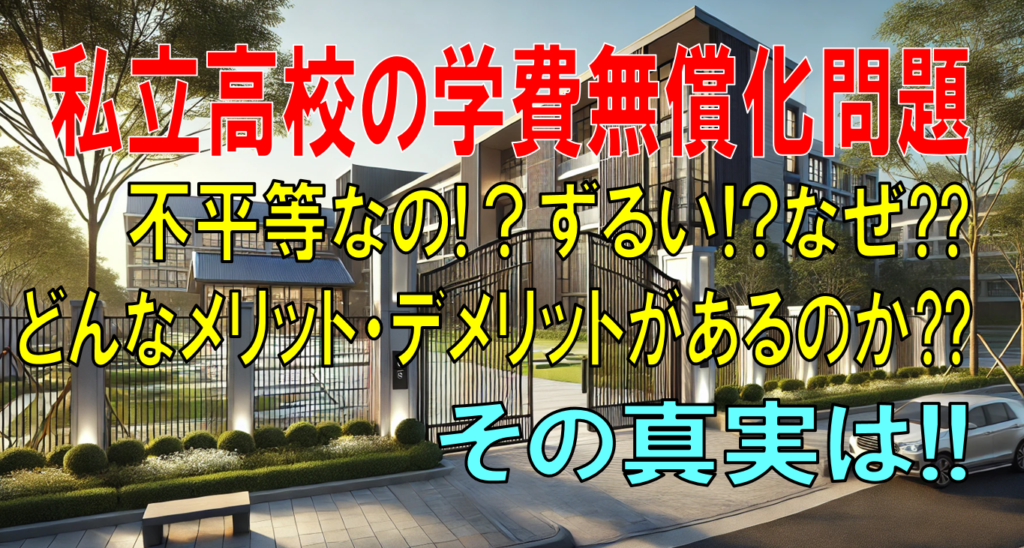

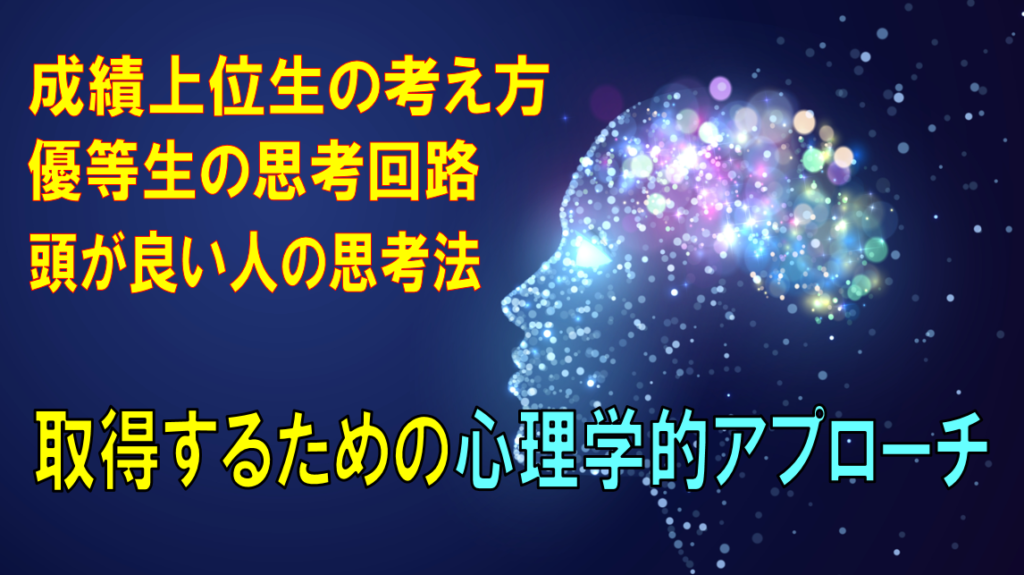


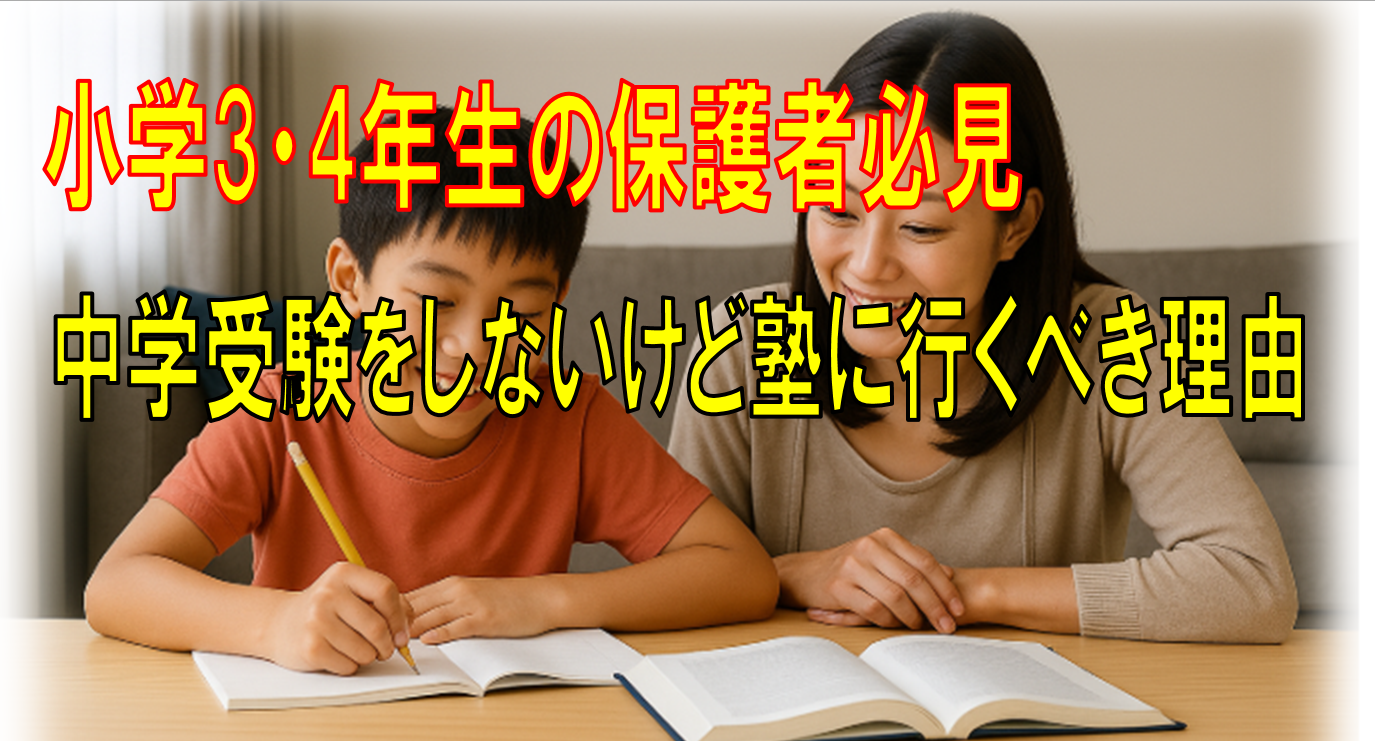
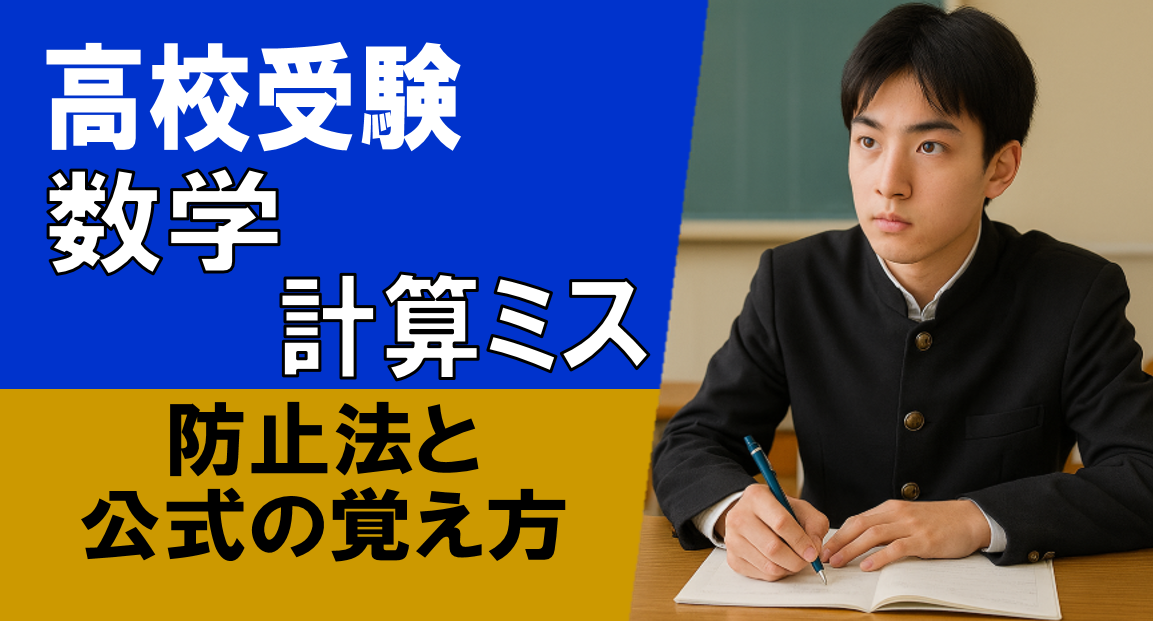

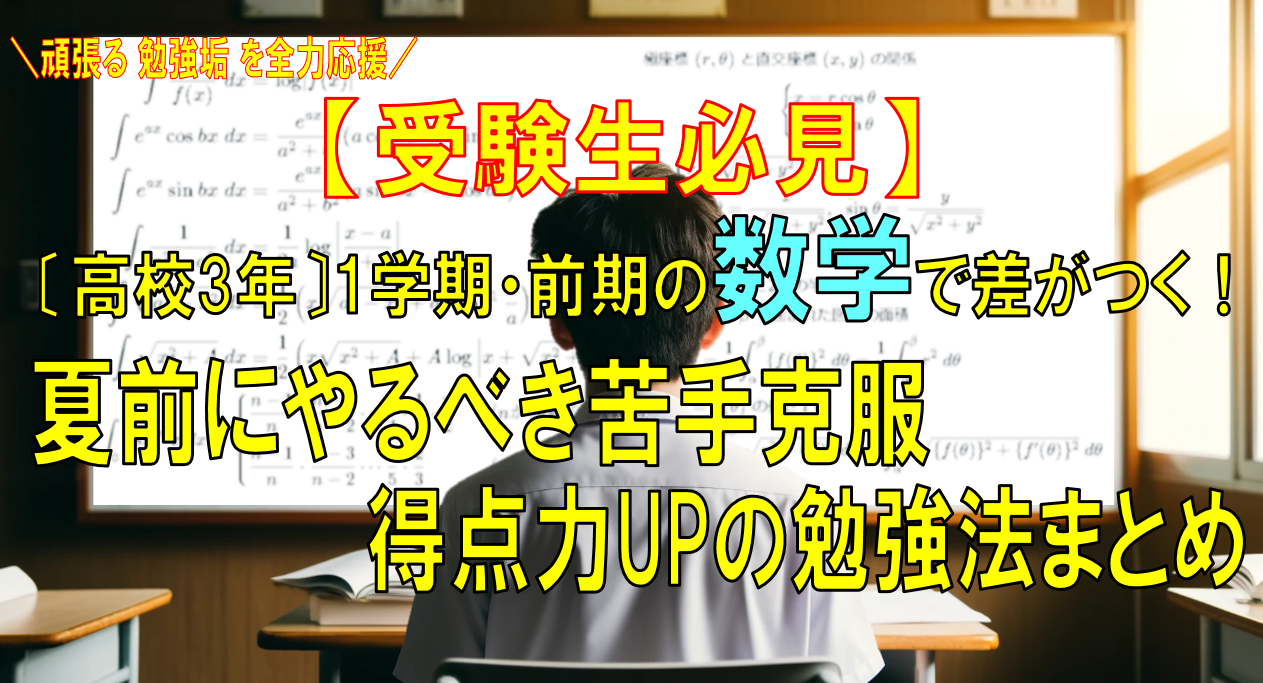
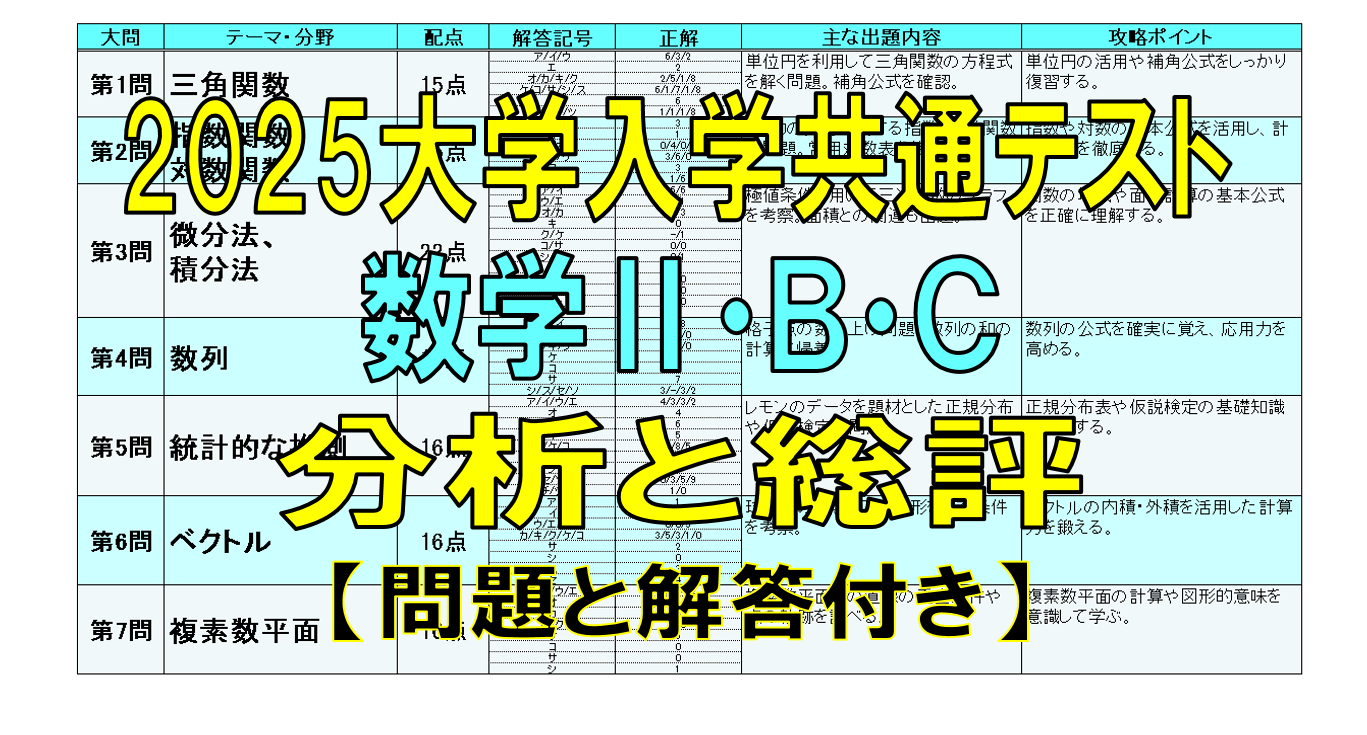
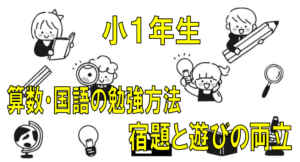
コメント
コメント一覧 (4件)
[…] \小学生の保護者必見!/ 小1生の勉強・宿題管理の難しさ【小学1年生】算数・国語の勉強方法/宿題と遊ぶの両立 […]
[…] 【小学1年生】算数・国語の勉強方法/宿題と遊びの両立 […]
[…] 【小学1年生】算数・国語の勉強方法/宿題と遊びの両立 […]
[…] 【小学1年生】算数・国語の勉強方法/宿題と遊びの両立 […]