中学受験しない小3・小4も塾に行くべき?塾講師から保護者に寄り添う想い
はじめに:中学受験しない子に塾は必要かと悩む親御さんへ
「うちは中学受験しないけど、塾に行かせようか迷っている」
「小学生のうちから塾は必要?」
「成績が落ちてきたけど、塾に行かせたほうがいい?」
小学校3~4年生くらいになると、周りで塾に通い始める子も増えてきます。中学受験の予定がなくても、「このままで大丈夫だろうか」「うちの子も塾に行かせた方がいいのか」と不安になる保護者の方も多いでしょう。私自身、塾講師歴22年で、かつて大手進学塾の進路指導統括責任者という経験を持ち、現在はプロの教育ブロガーとして多くの親御さんの相談に乗ってきました。その立場から結論をお伝えします。
本記事では、その理由を保護者の気持ちに寄り添いながら丁寧に解説し、安心してお子さんの学習環境を選択できるよう5つの根拠をご紹介します。さらに、お子さんの性格に合わせた塾の選び方(集団授業か個別指導か)についても触れます。
まず知っておきたいのは、今どき小学生の約4割がすでに塾に通っているという現実です。Amebaの調査によれば、小学生の約38%が塾通いをしており、さらに現在通っていない子の保護者でも「通わせたい」と考えている人が半数以上にのぼったそうです。つまり小学生の通塾は珍しいことではなく、多くの家庭が検討している選択肢なのです。
では、なぜ中学受験をしない子にも塾が必要だと言えるのでしょうか?以下で具体的な理由を見ていきましょう。
理由1:学校の授業ペースでは物足りない ― 公立小の授業は平均以下に合わせがち
まず押さえておきたいのは、学校の授業だけでは学力の底上げに十分でない場合が多いという点です。公立小学校ではクラス全体を一斉に指導する関係上、どうしても理解が遅い子にペースを合わせて授業を進める傾向があります。教師は「できない子を置いてきぼりにしてはいけない」というプレッシャーが強く、「できる子」を多少放っておくのは仕方ないとしても、「できない子」を置き去りにするのは絶対ダメという風潮があるためです。その結果、授業の進度や難易度はクラスの平均より下寄りになりがちで、半数くらいの子どもは「学校の授業は遅いな…」と感じてしまうことも珍しくありません。
学校側も努力はしていますが、一クラスの中で学力差が大きいと全員に最適なペースで教えるのは難しいのが現実です。最近では小学校で習熟度別にクラス編成をすることもありますが、それでも同じクラス内で「理解が遅い子はついていけず、理解が早い子は退屈してしまう」状況は解消しきれないようです。特に勉強が苦手な子への指導は、「とりあえず問題が解ければOK」「難しい問題で自信を失わせないようにする」といった方針になりがちで、本来身につけておきたい知識や技術を省略してしまうケースもあります。たとえば算数の「割合」の単元で本来教えるべき公式を簡略化したり、分数の足し算で通分が大変な問題は扱わないで済ませたり、といった具合です。こうした安易な妥協の積み重ねで、小学校の間に習得すべき学力の土台が十分築けないまま中学校に進学してしまう恐れがあります。
塾に通わせれば、この「学校の授業ペースの物足りなさ」を補うことができます。塾では少人数制や個別指導で、その子の学力に合わせて進度や内容を調整できます。学校で物足りなさを感じているお子さんにとって、塾は刺激と深い学びを提供してくれる場になるでしょう。逆に、学校の授業についていけていないお子さんにとっても、塾は復習や基礎固めの場として機能し、学校内容の理解を助けてくれます。つまり塾は「学校の授業についていけているか」「家庭で自主学習できているか」という点で不安がある場合に、その不安を解消する手助けとなり得るのです。
理由2:小3・小4の学習内容は難しく重要!今ここで遅れると挽回が困難
「小学3~4年生の勉強なんて、まだ基礎的な内容でしょう?」と思われるかもしれません。しかし実際には、小3・小4の学習内容は大人が思う以上に難しく、今後の学習の土台が詰まっています。例えば国語では習う漢字のレベルが上がり、同音異義語も増えるので、漢字テストで正しい答えを選べない子がちらほら出てきます。また算数では扱う数の桁が増えるため、ケアレスミスが格段に多くなる時期です。さらに小学3年生までは「生活」だった科目が、小学3年生の後期から理科と社会に分かれて本格的に始まるため、一気に覚えること・理解すべきことが増えます。こうした変化が積み重なり、「難易度の高い学び」がスタートする小学4年生に入る前から、子どもたちの間で学力差がつきやすくなるのです。
特に算数では小学3年生までに四則計算(足し算・引き算・かけ算・割り算)の基礎を学び終えるため、小4からはそれらを使った応用問題が増えて一気に難しくなります。もし小3までの内容でつまずきがあると、小4以降の学習で苦労するのは目に見えています。理科や社会も小4から専門的な内容に入り、暗記量・理解量ともに増大します。
問題は、この時期に一度ついてしまった学力差は、後から埋めるのが非常に難しいということです。塾講師の研修会で、「小学4年から始めるのはちょっと遅い。実際にはそれ以前から差が生まれており、一度開いた学力差を挽回する道のりは思う以上に険しい」と指摘しています。高学年や中学生になって「やっぱり基礎ができていないから塾に行こう」と思っても、その頃には定期テストや部活で忙しく、基礎に立ち戻って復習する時間を確保するのが難しくなってしまいます。実際、中学生になると約2~3ヶ月ごとに定期テストがあり、その勉強に追われてしまうため、穴があってもなかなか埋める時間が取れません。だからこそ、まだ時間にゆとりがあり柔軟性も高い小3・小4のうちに塾でしっかり学習の根幹を築いておくことが肝心なのです。
塾では学校より先取りして深く教えてくれる進学塾タイプから、学校内容の補習に重点を置く塾まで様々あります。中学受験をしない場合でも、小3・小4で塾に通って基礎を固めておけば、中学入学後にスムーズにスタートダッシュを切れるという大きなメリットがあります。高学年や中学生になって「もっと早くからやっておけば…」と後悔しないためにも、今のタイミングで塾を活用しておくことを強くおすすめします。
理由3:算数の演習量がカギ!計算力(スピード&正確さ)は低学年からの積み重ねで差がつく
小学校低学年から中学年にかけて、特に算数(数学)の計算力は演習量次第で大きな差がつきます。計算力とは単に答えを出す力だけでなく、「スピード」と「正確さ」の両方が求められます。得点力に直結するのが正確さなら、学習効率に直結するのは計算のスピードだと言われます。スピードが速ければそれだけ多くの問題演習を積むことができ、結果的に正確さも磨かれていきます。では、この計算のスピードと正確さは一朝一夕で身につくものかというと、答えはNOです。低学年から地道にトレーニングを積み重ねることで初めて身につくものだからです。
塾に通わせる最大のメリットの一つは、この「計算練習の圧倒的な量」を確保できることです。学校の授業や宿題だけでは演習量が足りず、家庭学習で補おうにも限界があります。しかし塾なら、計算ドリルやテキストでどんどん問題を解かせ、間違いはその場で先生がチェック・解説してくれます。
例えば公文式や学研教室のような計算特化型の教室では、小学生のうちに中学生レベルの計算問題まで先取りして練習する子もいます。その結果、計算問題に対する「圧倒的なスピードと正確さ」が身につき、中学以降の数学でも有利になるのです。実際に塾で鍛えた子は、文章題に入る前段階の計算処理が速いため問題演習の量をこなせて理解も深まりやすい、という好循環があります。
また、計算力だけでなく読解力や学習習慣といった学力の土台も、小学生のうちに塾で鍛えておくと「普通のレベル」を底上げできることは確実です。塾に通うことで勉強の習慣づけや勉強の方法、読解力・計算力を鍛えられるので、塾に行っていない子に比べて基礎学力のレベルを高く維持できるとされています。特に中学・高校と進むにつれ、授業スピードも速く内容も難しくなる中で、小学生の頃に身につけた計算力や基礎学力が「貯金」となって子どもを支えてくれるのは間違いありません。
要するに、小3・小4のうちに塾でたくさん演習を積んでおけば、中学以降で「計算に時間がかかってテストが解き終わらない」「基礎力不足で応用についていけない」といった壁にぶつかりにくくなるのです。算数のつまずきは早めに解消し、「計算は得意!」「計算なら任せて!」という自信を持たせてあげましょう。その自信が他の教科への前向きな姿勢にもつながります。
理由4:将来の高校受験も視野に―上位校合格者は早い段階から塾に通っている
中学受験をしなくても、最終的には高校受験が控えています。公立中学に進むお子さんの場合、高校受験が大きな目標になりますが、高校受験で難関・上位校を目指す生徒の多くは、中学入学より前、つまり小学生のうちから塾通いをスタートしているのが実情です。実際、難関高校合格者のデータを見ると、「塾に通い始めた時期が早いほど合格率が高い」という傾向がはっきり出ています。私のこれまでの分析によると、「早く塾通いを始めるほど、難関高校進学を実現できる率が高くなっている」ことは間違えないです。その理由は単純で、一般的な受験生より長い時間をかけて目的に合わせた勉強ができる分、成績も上がりやすく合格のチャンスが大きくなるからです。
もちろん、「難関校に行くつもりはないから関係ない」と思われるかもしれません。しかし、高校受験はたとえ地域の公立トップ校でなくても、それなりの競争があります。中堅レベル以上の高校に進学したいと考えるなら、中学校の内申点(定期テストの点数)で平均「4」以上は欲しいところですが、そのためには中1から定期テストで80点以上を安定して取るくらいの学力が必要です。小学校のテストで80点台だった子が中学では50~70点になってしまう例は決して珍しくなく、小学校のうちに90点以上取れる力をつけておかないと中学で苦戦する可能性が高いといえます。
早めに塾で学習習慣と基礎学力をつけておけば、中学に入ってからも定期テスト対策に余裕を持って取り組めます。特に公立高校受験では、県によっては中1・中2の内申点も合否に影響しますから、中学1年生の最初から好成績を収めておくことが後々効いてきます。小学生のうちから塾に通っていた子は、中学に入っても「勉強するのが当たり前」になっており、部活や遊びとの両立も上手です。それに対し、小学生時代に勉強の習慣があまりなかった子が中学で急にエンジンをかけるのは大変です。小3・小4から塾で積み重ねた勉強の貯金が、中学・高校でお子さんを支え、志望校合格への力となると考えると、早期スタートの価値を実感できるのではないでしょうか。
理由5:家庭でサポートしきれない部分をプロに任せられる安心感
「家で親が勉強を見てあげられるなら塾は必要ない」という意見もあります。確かに理想を言えば、毎日親御さんが付き添って宿題を見てあげたり、ドリルをやらせたりできればベストかもしれません。しかし現実には、共働きで平日は子どもの勉強を見てあげる時間が取れない家庭も多いです。夕方まで仕事で不在にしていれば、どうしても子どもの家庭学習を毎日見守るのは難しいですよね。
また、時間があっても親子だと勉強で対立してしまうこともよくあります。お恥ずかしながら、1000人以上の勉強を見てきた塾講師の私自身でも実は、例外ではありません。。。
よく親御さんから「つい感情的に怒鳴ってしまう」「子どもが反抗して勉強どころじゃなくなる」「先生の言うことなら素直に聞く」という声を聞いてきました。親が教えようとすると子どもが素直に聞いてくれなかったり、親の方も教え方がわからずイライラしてしまったり…。”身近な親子ゆえの難しさ”がありますよね。そうした負のスパイラルにはまるくらいなら、いっそ程良い距離感のあるプロの手に任せてしまった方が親子ともにストレスが減るという場合も多いのです。
塾の先生は教えるプロですし、客観的な立場でお子さんに接してくれます。塾に通わせることで、親御さんは家庭学習を無理に見てあげられない罪悪感から解放され、お子さんも「お母さん(お父さん)に勉強で怒られる」ストレスが軽減されるという効果も期待できます。実際、先輩ママ・パパの体験談でも「フルタイム勤務で下の子もいて、家だと宿題やらせるのに毎日ケンカになるから、回数多くて安い塾に入れて宿題だけでもやってもらうようにした」という声がありました。塾を上手に使うことで、家庭円満にもつながる面は見逃せません。
要は、「親のサポート」と「塾でプロのサポート」は二者択一ではなく、塾と家庭の双方からお子さんの勉強をサポートすることが重要です。親が見てあげられない部分を塾に任せ、塾での学習状況を家庭でフォローする――そうした役割分担をすることで、お子さんの学習を効果的に支えることができるでしょう。
集団塾と個別指導、どちらが向いている?~お子さんの性格に合わせた塾選び~
塾に通わせると決めた場合、「集団授業の塾」と「個別指導の塾」のどちらが良いか迷われるかもしれません。これについては、お子さんの性格や学び方の好みによって向き不向きがあります。大きく分けて指導形式は3種類(集団授業・個別指導・映像/オンライン)ありますが、ここでは代表的な集団と個別について、その特徴を簡単にまとめます。
- 集団授業の塾:学校のクラスのように一斉授業を行うスタイルです。同じレベルの子どもが集まり講義形式で進むので、周りの子と競争した方がやる気が出る子、講義形式の授業が好きな子、同程度の学力の友達と切磋琢磨したい子に向いています。競争心が勉強の原動力になるタイプのお子さんや、「負けたくない!」という思いが強いお子さんは集団塾で刺激を受けると伸びやすいでしょう。一方で授業の進み方や内容は集団全体に合わせるため、自分のペースでじっくり理解したい子には合わない場合もあります。
- 個別指導の塾:先生1人に生徒1~2人という形で、きめ細やかな指導を受けられるスタイルです。自分のペースで学習する方が好きな子、わからない所をその場で質問しながら進めたい子に向いています。人前で質問したり発言したりするのが苦手なお子さんでも、個別指導なら安心ですし、理解度に合わせて内容や宿題量も調整してもらえます。また、得意不得意の科目にばらつきがある場合や、特定の単元だけ重点的にやりたい場合も個別指導が適しています。反面、競争相手がいないので切磋琢磨の刺激は少なく、費用も集団より高めになりがちです。
どちらにもメリット・デメリットがありますが、一番大切なのはお子さんの性格や学習スタイルに合っているかどうかです。例えば、負けず嫌いで競争心が強い子を個別に入れるよりは集団の方が燃えるでしょうし、引っ込み思案でマイペースな子を大人数の塾に入れると萎縮してしまうかもしれません。塾選びの際はぜひお子さんと一緒に体験授業などに参加し、「この雰囲気なら頑張れそう」「この先生なら質問しやすい」と感じられるか確認することをおすすめします。
また最近はオンライン指導や映像授業も選択肢として増えています。習い事やスポーツで忙しく決まった時間に通塾が難しい子、自宅で好きな時間に学びたい子には、タブレットやパソコンで受講できるオンライン塾も検討すると良いでしょう。通塾の送り迎えの負担がないのもオンラインの利点です。ただし低学年の場合は対面の方が集中しやすい子も多いので、性格と年齢に合わせて検討してください。
参考記事:

\これでもう迷わない!/
いずれにせよ、小学生の塾選びで一番大切なのは「子どもの性格・興味関心・目的に合った塾を選ぶこと」です。お子さん自身が「ここなら頑張りたい」「この先生に教わりたい」と前向きに思える塾こそがベストです。親の希望だけを押し付けず、お子さんとしっかり話し合って決めてくださいね。
おわりに:親が寄り添い、早めの一歩で未来の学びを支えよう
中学受験をしない小学生に塾は必要か――この問いに迷う保護者の気持ちに寄り添い、5つのポイントからお話ししてきました。
小学校3~4年生という時期は、一見のんびりしているようで実は学力のターニングポイントです。ここでの習得度合いが、後の中学・高校の学習に大きく影響します。「うちの子は公立中学に行くし、今は遊びも大事だから…」というお気持ちもよくわかります。もちろん遊びや習い事、家族の時間もしっかりと取り大切にしつつ、週に数回でも塾という環境で勉強する習慣をつけておくことで、お子さんの将来の可能性を大きく広げることができます。
多くの保護者の方は、はじめは皆さん悩みながら決断されています。ただ一様に感じるのは、早めに手を打ったご家庭ほど「勉強は早く始めて損はない」「早くからやって良かった」と安心されているということです。お子さんが小さいうちから勉強の習慣が身につけば、中学・高校で勉強が本格化したときも余裕を持って対応できますし、何よりお子さん自身が「できる自分」に自信を持てます。それは勉強に限らずポジティブな自己イメージにつながり、健やかな成長にも繋がるでしょう。
最後にもう一度強調します。塾は決して中学受験する子のためだけのものではありません。 中学受験しない子にとっても、塾は学びをサポートし伸ばしてくれる強力な味方です。学校と家庭だけでは得られない刺激や経験、そして確かな学力の積み重ねを提供してくれます。親御さんとしては、最初は送り迎えや費用の負担など心配もあるかもしれません。それでも、お子さんの未来への投資と考えてみてください。小3・小4からの塾通いが「勉強って面白い」「努力すればできる」という成功体験を積むきっかけになり、長い学びの道を歩む原動力になるはずです。
お子さんの笑顔と成長のために、ぜひ前向きに検討してみてくださいね。私も一人の親として、そして教育に携わる者として、頑張るお子さんと支える保護者の皆さんを心から応援しています。
参考文献・出典: 小学生の塾通いに関する調査データterakoya.ameba.jp、学校授業の進度と学力差に関する解説softtennis-blog.com、教育ブロガーによる学力差と「小4の壁」の分析edumother.comedumother.com、大手塾による難関高校合格者の分析eikoh.co.jp、塾選びのポイントに関する記事terakoya.ameba.jpterakoya.ameba.jpなどを参照しました。各種データや専門家の意見を踏まえ、本記事では中学受験をしないお子さんにも早めの塾通いをおすすめしています。ぜひご家庭の状況に合わせてご判断ください。頑張るお子さんとご家族にエールを送ります!

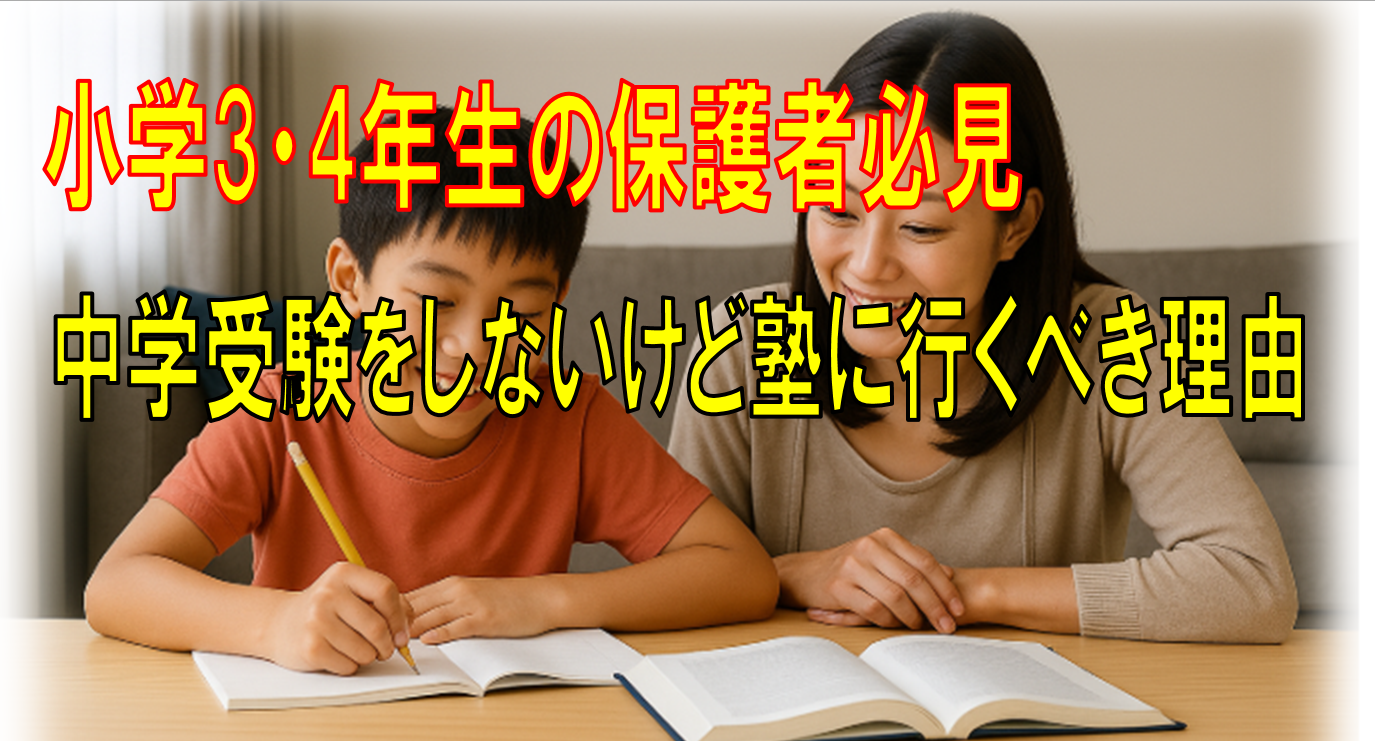
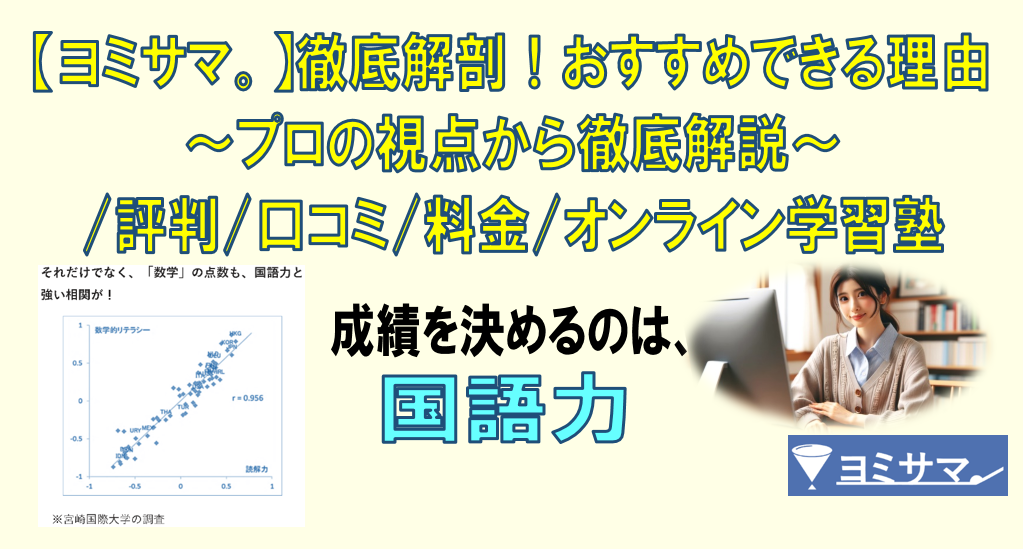
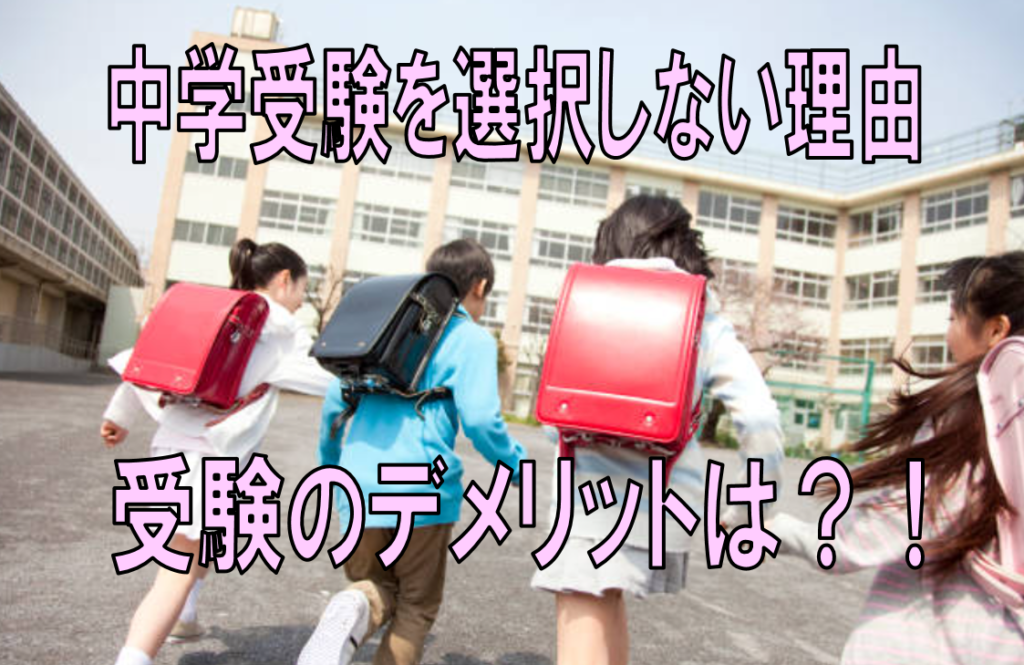
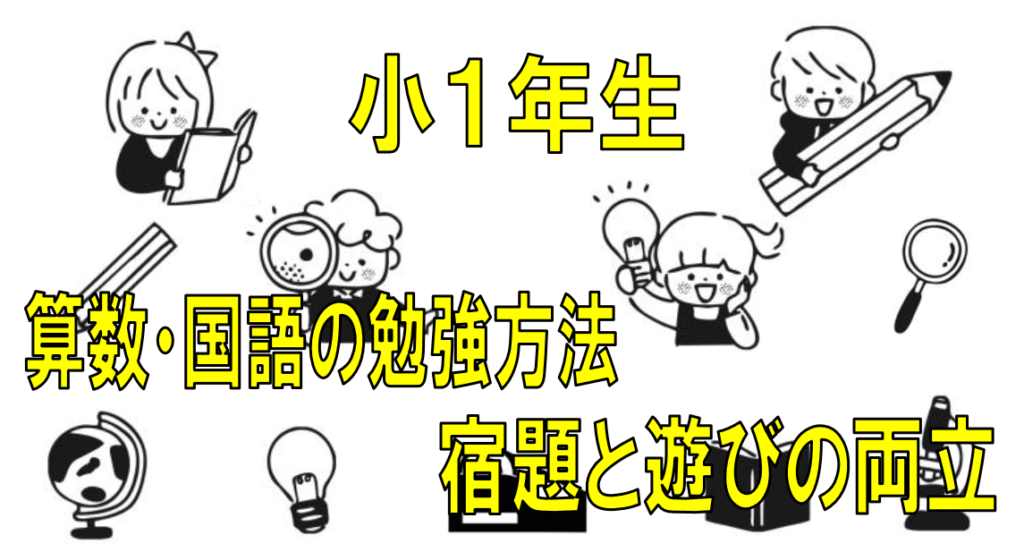
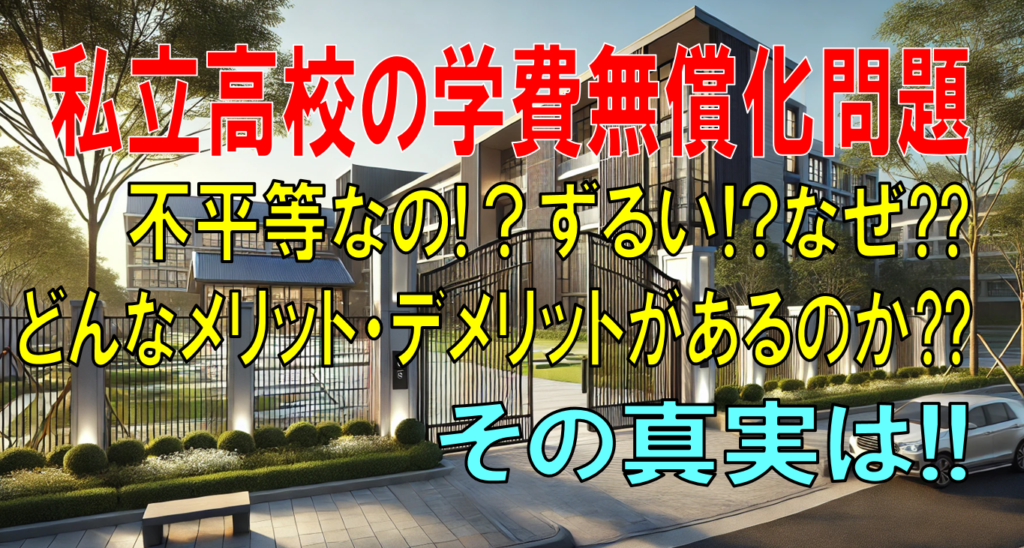
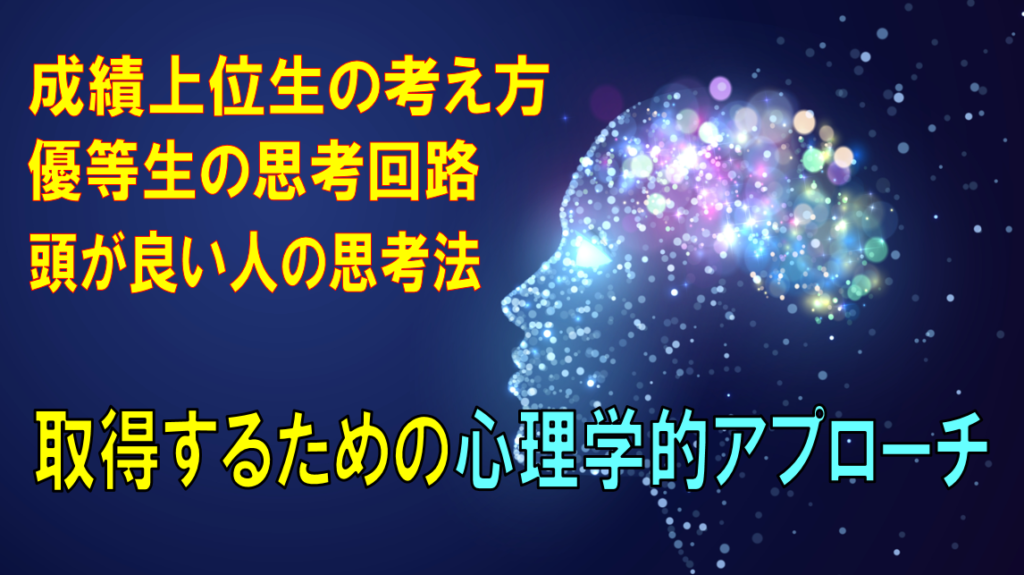

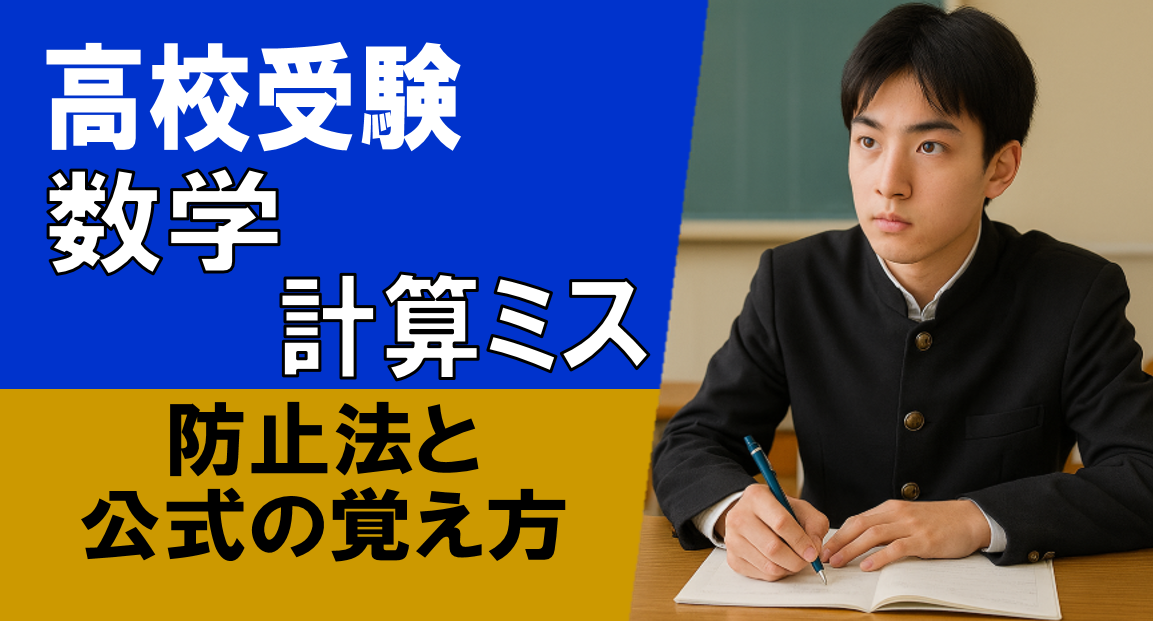

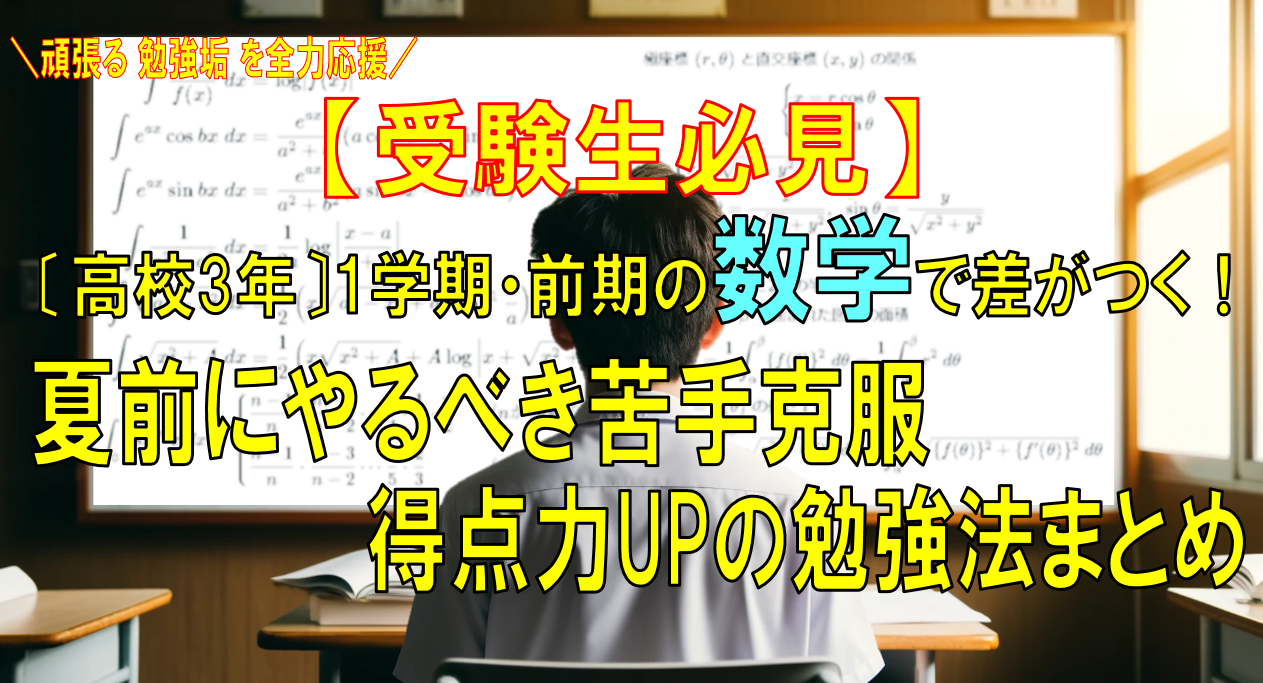

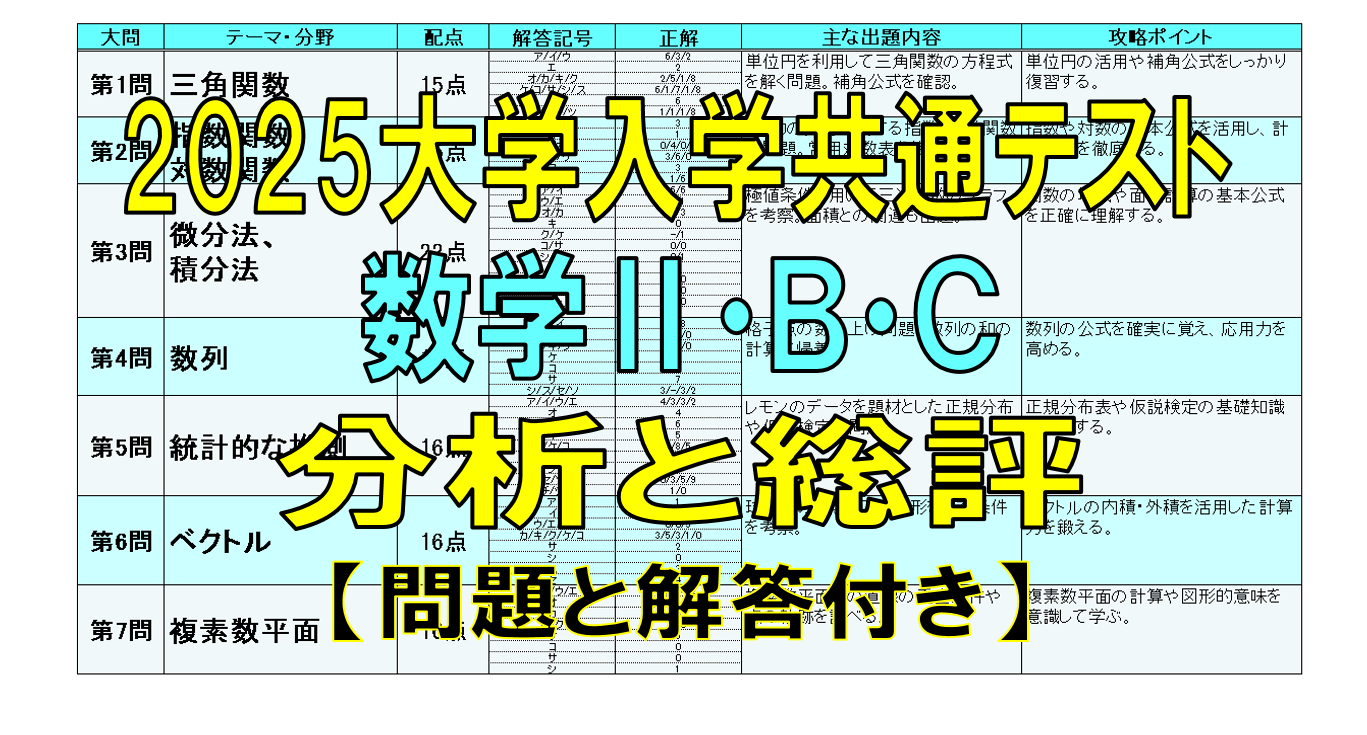
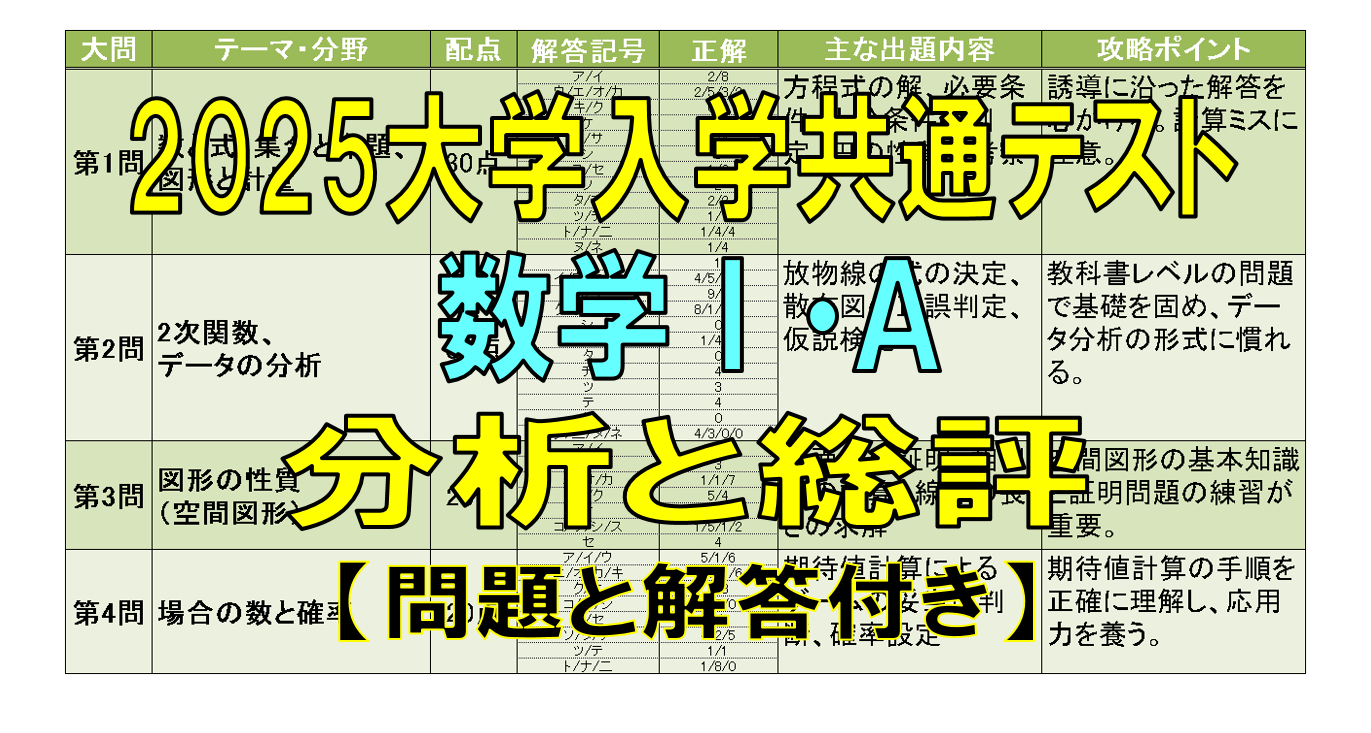
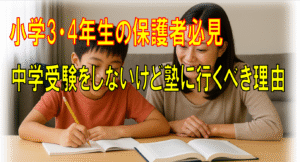
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 中学受験をしない小学3・4年生でも塾に行くべき理由 […]
[…] 中学受験をしない小学3・4年生でも塾に行くべき理由 […]